倉橋日出夫著「古代出雲と大和朝廷の謎」を読む ―4(完)― 出雲族も天孫族も朝鮮半島から、中国の「天(神)」概念vs出雲系の土着の神、万葉集は記紀神話を無視、鏡の神仙思想は卑弥呼の鬼道なのか
倉橋日出夫著「古代出雲と大和朝廷の謎」を読む ―4(完)― 出雲族も天孫族も朝鮮半島から、中国の「天(神)」概念vs出雲系の土着の神、万葉集は記紀神話を無視、鏡の神仙思想は卑弥呼の鬼道なのか
「第11章 美輪山と出雲の神」
p209
日本海を使った交流は相当に早くからあり、北部九州を経由しない独自の交易ルートを
もっていたのではないか、と考え始めているのである。
このような日本海を使った人々の交流は、縄文時代か、あるいはそれ以前までさかのぼる
ものだ。
・・・最も古いものでは、1万年から2万年前の東北地方の石器が出雲でみつかっている。
==>> ここで、古代の出雲と東北の関係を書いているサイトはないかと検索
してみたところ、興味深いものが見つかりました。
東北の基層文化を探る ― 東北出雲説と八郎太郎伝説
http://www.forest-akita.jp/data/kiso-bunka/kisobunka04/kiso-04.html
「松本清張の小説「砂の器」では、秋田の亀田と同じズーズー弁を話す地域が
島根県の亀嵩にあった。つまり出雲弁もズーズー弁なのである。実際に出雲弁を
何度も聞いたことがあるが、確かに東北の人だと錯覚するほど似ている。それに
しても、なぜ東北から遠く離れた出雲が飛び地状にズーズー弁を話すのであろ
うか。」
「産後の胎盤-エナの埋め方の違い・・・東日本は、縄文以来、戸口に埋める習俗
がある。西日本は、弥生以来、産室の床下・縁の下に埋める風習が広く分布して
いる。おもしろいことに、その例外が出雲地方で、東日本と同じ習俗をもってい
るという。」
「岩手の作家・高橋克彦氏は、大陸から渡ってきたヤマト族に出雲の和人が敗れ
て、畿内から遠い九州あるいは東北方面に逃れた。そのうち「北へと逃れ、新た
な民族を形成していったのが東北人のルーツ」だと、東北出雲説を主張して
いる。」
「男鹿市船越の八龍神社には、八郎太郎伝説の主・出雲系のヤマタノオロチを
祀っている。この八郎潟の神は、出雲系でズーズー弁とも一致する。」
他には、「知られざる出雲と東北の遺伝的類似性」というサイトもありました。
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=2586
・・・単なる交易の為の交流という以前に、出雲と東北には根本的な
ところでの繋がりがあったようです。
p214
大和の信仰の中心である三輪山の大神神社は、大物主神を祭っている。
大物主神は、因幡の白ウサギなどでおなじみの大国主命の別名で、出雲系の神である。
三輪山信仰がいつから始まったのか明らかではないが、おそらく大和朝廷より前、さらに
邪馬台国より前の、2千年かそれ以前にまでさかのぼるのは間違いない。
大神神社には本殿がなく拝殿があるだけで、ご神体である三輪山そのものを拝むように
なっている。
==>> この著者は、大物主神(おおものぬしのかみ)と大国主命(おおくにぬしの
みこと)は同じ神様であるとしているのですが、私はまだ納得できて
いない点があります。
こちらのサイトでは、大物主神には多くの別名があると述べているのですが、
同時に、以下のような説明があります。
大物主神(オオモノヌシ)とは?
ニギハヤヒや大国主と同一説のある謎の多い神様を解説!
「日本書紀や古事記の中で、大物主神(オオモノヌシ)は、
「ヤマトの国の三輪山に私を祀れ」と大国主命(オオクニヌシノミコト)に伝えた
と表記もあり、神代のころからの由来がはっきり見られる神社です。」
「この物語は、大物主神(オオモノヌシ)が天皇家と姻戚関係にあることを表し、
皇室にもとても大事な神様であることを伝える話です。」
・・・AさんがBさんに指示を出しているわけですから、別人だろうと
思うんですが・・・・神々の世界は常識を超えているってことでしょうか。
p216
神社の起源は、普通、このような磐座(いわくら)にあると見られている。 八百万の
神が集まることで知られる出雲大社も、もともとは巨石を祭った磐座の祭りが行われて
いあといわれている。 鎌倉時代の絵図によると、出雲大社の背後には巨石のような
ものが描かれていて、それが磐座だったようである(「古代出雲文化展」図録)。
==>> 「「出雲の磐座」という検索で見つけた、それらしき写真はこちらです。
https://ameblo.jp/goldforest33/entry-12198669839.html
「出雲大社の本殿の後ろに「八雲山」という山があります。 実はこの八雲山
こそが出雲大社の御神山であり、御神体そのものなのです。」
本来の神社の姿ということでは、先に読んだ本に、三輪山の磐座の話が
ありました。
岡谷公二著「神社の起源と古代朝鮮」を読む
―3―三輪山の磐座こそが本来の神社、新羅=出雲=邪馬台国vs大和朝廷?
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/09/blog-post_30.html
「p144
奈良県桜井市にある三輪神社(大神(おおみわ)神社)は、三輪山(三諸
(みむろ)山)を神体とし、本殿がなく、神体山を直接拝するという太古の神社
のありようを今に伝えていて名高い。
朝廷からは伊勢神宮と並ぶ崇敬を受け、見る者をたちまち古代へと誘う三輪山
の山容や、広い禁足地を含む閑寂で清らかなその社域とは、多くの人々の心を捉
えてきた。三輪神社が、神社の原初のありようを考えようとする時決して逸する
ことのできない存在であり、神社の典型の一つであることを否定する者はいな
いだろう。」
・・・このような話を今までに読んできたものだから、
「本殿の無い三大神社」、金鑚(カナサナ)神社、諏訪大社、大神神社を
参拝して歩こうということにしたわけです。
とりあえず、近いところから順番ということで、金鑚神社と諏訪大社は
すでにお参りしましたので、残すは大神神社ということになります。
金鑚(かなさな)神社
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/jr.html
諏訪大社・四社参り
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/jr_28.html
p220
私は以前、・・・中近東文化センターというところで、シュメール語やヒッタイト語など、
古代中東の楔形文字(くさびがたもじ)を読む講座に数年間参加していた。
「ヒッタイトの楔形文書のひとつに『ヒッタイト法典』がありますが、そのなかでは、
『蛇を使って呪術を行なったものは死刑にする』と書かれています」
講座のなかで、そういう話を聞いたのである。
p221
・・・つまり、蛇の呪術は、死刑に値するほど邪悪なものとみなされていた、ということで
ある。・・・これは古代の蛇信仰の重要な一面をあらわしていると私は思う。
==>> シュメール語と蛇神ということになると、先に読んだこちらの本を
どうしても思い出します。
日本の古い神道などは、すべてシュメールのギルガメッシュ叙事詩が元に
あるという説でした。
川崎真治著「謎の神 アラハバキ」を読む
―2(完)―日本の古神道はメソポタミアからの外来種? 伊勢神宮のハハキ神
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/blog-post_1.html
「p161
吉野女史は、蛇木、竜樹がハハキであると解釈した。
それに対して、私はハハキを「ハハ」と「キ」に分け、「ハハ」は「母」である
と解釈した。
また吉野女史は、ハハキの「キ」を「木」「樹」と解したが、私は木、樹では
なく「地」であると解した。 すなわち、シュメールの地母神、蛇女神のキ(地)
が、ハハ・キのキであると。」
そして、卑近な例でいえば、私の地元にある興禅院の境内にある弁財天の
鳥居の両脇には、狛犬でも狛狐でもなく、狛蛇(白蛇)が鎮座していました。
川口市安行散歩: 宝厳院の仁王門、興禅院の十三仏、金剛寺の藤棚
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2021/07/blog-post_9.html
こちらのサイトでは、日本独自の弁天信仰であるとの説が書かれています。
弁財天(弁才天)とは|弁天様のご利益や信仰の歴史、祀られる神社をご紹介
(https://shinto-bukkyo.net/category/bukkyo/%e5%a4%a9%e9%83%a8/ )
「弁財天(弁才天)はインドの神様が由来となっています。」
「弁財天(弁才天)という神様は、インドで発祥した仏教にインドで仏教が始まる
以前から信仰されてきたバラモン教・ヒンドゥー教の神様が取り入れられた
のが始まりです。」
「宇賀神(蛇神)と弁財天(弁才天)が習合する」
「弁財天(弁才天)のお使い(眷属)が蛇と考えらるようになったのは、弁財天
(弁才天)と宇賀神が同一視されるようになったように、水の神・豊穣の神という
ご神格があったことからと考えられています。」
上記のサイトでは、蛇神は日本独自の弁天信仰とも書いてあるんですが、
インド神話の「ナーガ」という蛇王のサイトを読むと、日本独自というのは
どうなのかなという気もします。
https://www.karakusamon.com/naga.html
「蛇神崇拝はすでにインダス文明において存在したと推測される。
アーリヤ人は古来より行われた蛇神崇拝をしだいに受け入れ,
半神の一つとみなすようになった。
ヒンドゥー教の文献では,ナーガすなわち蛇族は,
パーターラと呼ばれる地底
界に住むとされる。バースキその他の竜王がその世界を統治している。」
p222
記紀神話に貫かれている理念というのは、天つ神(あまつかみ)対国つ神(くにつかみ)
という対立関係によくあらわれている。 天つ神を国つ神より上に置き、天つ神の御子で
ある天皇の権威を高め、それによって国家統治の起源と由来を合理的に説明しようとする
のである。
p223
当時の朝廷の貴族たちは、たぶん中国に由来する「天(神)」という新たな概念を
持ち込んで、出雲系の神をローカルで土着の国つ神と位置づけたようである。
それまで一般的に普及していた出雲系の呪術的な信仰形態に、天照大神をシンボルに
した新しい天的な概念を持ち込んだのだろう。
直木孝次郎さんが『日本神話と古代国家』で述べているところによると、『万葉集』の
なかで歌われる神はおもに出雲系の神であり、「天照大神を主神とする記紀の神話体系
は、万葉の人々に無視されていたと考えなければなるまい」という。
いわば、出雲文化圏のようなものが早くから存在していたのではないか。 邪馬台国も
そのような土壌の上に乗っていたに違いない、と考えられるのだ。
==>> 大和朝廷の意図というのは、その通りであろうと思うのですが、それにしても、
天皇のお膝元ともいえる宮廷を中心とした場所で歌われていた万葉集が
ほとんど記紀の神話体系を無視していたというのも、なんだか不思議な感じ
がします。
出雲文化圏というのが、どのような拡がりを持っているのかイメージが
つかめないので、便宜上、こちらの邪馬台国・出雲説のサイトで
その範囲を捉えてみることにします。
古代出雲の特徴
「出雲と言っても、現在の出雲平野だけでなく、山陰地方全体だと捉えられて
います。山陰地方と言っても広大な地域ですが、平地が非常に少なく、邪馬台国
の候補地とされているのは、出雲平野だけです。」
「出雲の特徴としては、九州や朝鮮半島と強い繋がりがある事です。九州とは
土器や青銅器の交流、朝鮮とは鉄器や墳丘墓の繋がりが伺えます。青銅器につい
ては日本一の出土量、墳丘墓については個性的な四隅突出型墳丘墓が特徴的
です。」
p224
東日本の大きな神社はなぜ出雲系が多いのか、ということがある。
埼玉県大宮市(現さいたま市)の氷川神社、御柱で有名な長野県の諏訪大社、東京都
府中市の大国魂神社など、東日本には出雲系の神さまを祭る神社が多い。
列島には出雲を宗教的な故地とする出雲文化圏のようなものが存在していたのではないか。
ところが、どうもそれだけではないように思える。出雲そのものは弥生時代の新しい
勢力ではなく、もっと古い縄文文化ともつながっているのではないかーーー。
縄文文化を土台とする宗教文化圏が列島にはかつて存在し、出雲がその拠点となって
いたのではないだろうか。
==>> う~~ん、こりゃあますますロマンが膨れますねえ。
その文化圏の宗教的特徴が 磐座を祀る、「本殿の無い三大神社」に
象徴的に残っているって話になるのでしょうか。
p225
少し気になっていることを述べておきたい。 それは三輪山の大物主神と大国主神の
関係についてである。
大国主神が国譲りを承諾したあと、天神系の経津主神(ふつぬしのかみ)が各地を
平定してまわり、国つ神のなかでも従わないものは斬り殺し、帰順するものには褒美を
与えた。そのときに帰順したのが出雲系の大物主神と事代主神(ことしろぬしのかみ)
であった。
このとき大物主神は高天原の高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)のもとに呼び出され、
次のようにいわれる。
「もし、お前が国つ神を妻にするなら、お前はまだ私に心を許していないとみなす。
私の娘を妻にして、八十万神とともに、長く皇孫を守ってほしい」
・・・大物主神は、国つ神のなかでは大和朝廷にとって、比較的都合のよい神だったようで
ある。
==>> 私も大物主神については、大国主命と同一の神というところからなんだか
納得できないなと思っているんですが、著者もここで、その不思議な神の
謎について改めて書いているようです。
しかし、日本書紀にも古事記にも、あまり出てこないので判断が難しいよう
です。
ところで、上の部分で気になったのが「八十万神」という言葉です。
今であれば「八百万の神」というのが一般的ですから、一桁数字が違うのが
気になります。
こちらのサイトの解説によれば、読み方は「八十万神(やそよろずのかみ)」
だそうです。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AB%E7%99%BE%E4%B8%87%E7%A5%9E-874603
「八百万神【やおよろずのかみ】
数多くの神,すべての神のこと。類似の語に八十神(やそがみ),八十万神
(やそよろずのかみ),千万神(ちよろずのかみ)がある。森羅万象に神の発現を
認める古代日本の神観念を表す言葉。」
p230
古代においては、神を祭っておく神殿はなかった。 神さまは普段、山の奥や海の彼方
にいて、決まった季節になると迎えるものだった。
沖縄などでは、今も海の彼方から神さまを迎えている。
したがって、今日のように神社の建物の中に恒常的に神を祭っておくようになったのは、
ずっとのちの時代のことで、確実な例は7世紀の伊勢神宮からにすぎない。
==>> はい、これなんです。 私が今興味を持っているのは、大和朝廷以前の
時代の日本の古い宗教がどんなものだったかということなんです。
沖縄の御嶽(うたき)というものが、そのひとつではあるようですが、
それ以外にも、アラハバキ神とかミシャクジ神とか、訳の分からない神さま
たちがいたようで、そこが知りたいんです。
沖縄を含め、古代の神の祀り方については、すでに読んだ本の中に以下の
ように書かれていました。
岡谷公二著「神社の起源と古代朝鮮」
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/09/blog-post_23.html
「p134
古代の神社には、社、つまり建物はなく、森、或いは巨岩を神の依り代として
祀ったことについては多くの証拠がある。 人工の建物を神域内に設けることは、
神意にそむくことであった。 社を立てたために神の怒りにふれたとは、あちこ
ちの式内社について言い伝えられている。
たとえば、本殿がなく、三諸山を神体として拝するので有名な奈良の三輪神社に
関しては、平安後期の歌人藤原清輔の書いた「奥義抄」の中に・・・・・
社殿を含め、形あるものを嫌うとは、神社信仰の一つの大きな特色である。
たとえば神社には、神像というものは存在しない。
p135
今なお多くの人々の心の底に、意識されないながらひそんでいると思われる。
社殿のない、森だけの神社、聖地が点々と存在することは、そのあらわれであろ
う。若狭のニソの社、近江の野神の森、蓋井(ふたおい)島(山口県)の森山、
対馬の天童山、壱岐のヤボサ、薩摩・大隅のモイドン、種子島のガロー山、奄美
の神山、沖縄の御嶽・・・。」
・・・と言うことになると、今の神社のような本殿などの建物を整備して
いわゆる神道というものにしてきたのは大和朝廷の政治的な意図に基づく
ものだということなんですね。
そして、その前から祀られていた神々は、神社によっては客人(まろうど)神と
してひっそりと祀られているという形なんでしょうか。
もっとも、元々の古い神さまが新しい神さまに場所を乗っ取られた
形が一般的なもののように見えますが・・・
客人社と荒波々幾神を祀る神社一覧
http://kamnavi.jp/jm/arahaba.htm
「アラハバキが門を守る仕事をするのは、宮門を守る大伴、佐伯両氏や豊石窓神、
櫛石窓神と同様である。しかしそれだけでアラハバキの性格を言い尽くしたこ
とにはならない。というのはアラハバキを神として祀り、それを門客人神として
いる神社がいくつもあるからである。門神というならばともかく、門客人神と
いうのは、神社の門におかれた客人神ということであるから、随身または随神と
いう脊属の神を指すのではなく、客分という身上の神であることは明らかであ
る。この言葉は柳田、折口、中山などの指摘するように、地主神がその土地を
うばわれ、後来の神と主客の立場を転倒させて、客神となったことを物語ってい
ると思われるのである。」
「武蔵 足立 氷川神社摂社門客人神社「足摩乳命、手摩乳命」
古くは荒脛巾神社と号した。埼玉県さいたま市大宮区高鼻1
武蔵 多摩 大國魂神社摂社坪宮 「兄多毛比命」祭神はかってはアラハバキ神
であったと推定されている 東京都府中市宮町3-1
伊勢 宇治 伊勢神宮別宮荒祭宮「天照坐皇大御神荒御魂」
三重県伊勢市皇大神宮域内 *3p72
出雲 神門 出雲大社摂社門神社(東)「宇治神」、門神社(西)「久多美神」
古社図では門客人社と呼ぶ。島根県簸川郡大社町杵築東195」
・・・このリストに信濃の国・諏訪大社関係がないのは何故なんでしょうか・・
p232
出雲の神々は、始祖のスサノオと国土開発の英雄オオクニヌシを主人公にしているが、
最後には天孫族に屈伏し、国の支配権を譲るのである。
p233
記紀では、スサノオが乱暴狼藉を働いたために高天原を追放され・・・
・・・出雲の斐伊川のほとりに天降ったスサノオは、川に箸が流れてきたのを見て、
櫛名田比売(くしなだひめ)を知り、・・・八俣の大蛇を・・・
p234
この説話のなかに、すでに箸と櫛という百襲姫(ヤマトトトヒ・モモソヒメ)の三輪山
伝説のモチーフが登場しているのが面白い。『魏志倭人伝』によると、当時の倭国では
まだ箸を使わず、人びとは手で食べていたという。 箸はまだ珍しいもので、一種の
文化的シンボルでもあったようだ。
p235
巨大なオロチをスサノオが斬り殺しているというストーリーそのものだ。 蛇は呪術の
シンボルである。 八俣の大蛇はその代表ともいえる呪術の権化である。
出雲族の始祖スサノオは、まず葦原中つ国(日本)にやってきて、呪術をコントロール
できる存在として自分をアピールしたわけである。
==>> ふ~~ん、なるほど。 古い宗教である卑弥呼の鬼道というのが、
この蛇の呪術ということになるのでしょうか。
そして、百襲姫(ももそひめ)は、新しい文化的シンボルである箸を
大事なところに刺して、死んでしまう。
Wikipediaによれば、
この百襲姫は、倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)で、
「第7代孝霊天皇皇女で、大物主神(三輪山の神)との神婚譚や箸墓古墳
(奈良県桜井市)伝承で知られる、巫女的な女性である。」
・・・巫女的な女性というのが呪術という意味でポイントになりそうです。
その後、この百襲姫に代わって、大田田根子が採用されたようです。
「崇神天皇8年12月に天皇は、大田田根子に「大神」(おおみわのかみ)を祀ら
せた、という。この大田田根子が三輪君の始まりだという。」
p238
『日本書紀』の第四の一書では、オオナムチは最初、朝鮮半島の新羅に天降ったのち、
出雲にきたと伝えている。 オオクニヌシやオオナムチという名は、もちろんひとりの
人物を意味するのではなく、出雲族と総称できるような渡来人の動きをシンボル化した
ものだろう。
『出雲国風土記』には有名な国引きの説話がある。 出雲は細い布のように狭い土地
なので、新羅、高志の国(北陸)、隠岐など四つの地方のあつまった土地を引いてきた
というのである。
これはおそらく山陰から北陸にいたる地域、そして、朝鮮半島の新羅にもつながる
出雲族の活動範囲を示している。
また、天孫族が出雲族に国譲りを迫ったとき、それに反対したオオクニヌシの息子の
ひとりは、長野の諏訪まで逃げている。
==>> 著者は、出雲族の活動範囲を上のように推理しています。
それは、朝鮮半島からの渡来人でもあることを示唆していますし、
長野県の諏訪大社が、出雲族に乗っ取られて、諏訪の元々の神々に
実権を握らせながら、権威はたもつ形を作ったように見えます。
まずは、「国引き神話」を動画でみておきます。
出雲国風土記・国引き(島根半島の成り立ち)&宍道湖の夕景
https://www.youtube.com/watch?v=Tbo2K1IzwYI&t=68s
この長野県の諏訪大社にまつわる、縄文時代からともいわれる古い信仰と
ミシャグジ神(精霊信仰?? 地主神)との関係などが、こちらの動画サイトに
ありましたので、チェックしておきます。
お諏訪さまの謎に深く迫る! 建御名方神はお諏訪様なのか?
https://www.youtube.com/watch?v=uygAmVR63w0&t=513s
(この動画の内容をかいつまんで下に書きます)
「守矢氏が現人神・大祝を誕生させていた。
諏訪明神の衣を着せて諏訪明神の化身となる儀式がある・・・
諏訪大社の上社の重要な18の摂末社も詣でてそれぞれ即位式の儀式を行う。
その摂末社には、もともと諏訪の土地神様たちが祀られている。
外来の諏訪明神とその土地の神様の融合がここで行われていた。
また、神長である守矢氏はミシャグジ神も担っていた。
つまり、これら3つの神々を融合させている。」
上の動画で諏訪明神というのは、出雲から逃げてきたタケミナカタノカミ
ということになっています。 出雲から来たから外来の神ということですね。
建御名方神(たけみなかたのかみ)
https://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E5%BE%A1%E5%90%8D%E6%96%B9%E7%A5%9E-560167
「信濃の諏訪まで逃げ,国土を譲り渡すことに同意したのちにその地に鎮座した,
と伝える。現在もこの神は諏訪大社(長野県茅野市の上社前宮,諏訪市の上社本宮,
下諏訪町の下社春宮,下社秋宮)に祭られている。」
せっかくなので、ここで、大国主命を祭る、いわば出雲系とでもいえる
著名な神社を揚げておきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E4%B8%BB
出雲大社(島根県出雲市)
大國魂神社(東京都府中市)
氷川神社(埼玉県さいたま市)
小国神社(静岡県周智郡)
諏訪大社 境内 大国主社、秋宮恵比寿社(長野県諏訪市、諏訪郡)
大神神社(奈良県桜井市)
p244
『出雲国風土記』では、出雲族は葦原中つ国を天孫族に譲り渡している。
逆にいうと、天孫族は出雲族からそれを奪っている。列島の支配者としては最初に
出雲族がおり、そのあとを天孫族が奪った構図がある。
松本清張も、1970年代初め頃に・・・
「南朝鮮系のいわゆる『天孫族』が大和盆地に侵入してこない前は、畿内一円から紀伊半島
にいたるまで先住民の勢力地であった。 この先住民は、(朝鮮半島の)日本海沿いの地方、
のちの新羅地方から出雲地方に上陸してきて、但馬、吉備、山城などを回廊として畿内や
南紀にひろがり、一方は越前、越後など裏日本に流れたらしい。だが、かれらは、将来の
有力な天孫族のために畿内を奪われ、(略)出雲に後退を余儀なくされた・・・」(「遊学
疑考」)
==>> ここで松本清張の推理が出てきていますが、これは一世を風靡した
いわゆる「騎馬民族説」が前提となっていることを著者もコメントしています。
いずれにせよ、松本清張は、出雲族は新羅からの渡来系で、先住民と
なったけれども、その後後から入ってきた天孫族に追われて出雲に後退
したと推理しています。
しかし、天孫族がどのような出自のグループかは、ここでは書いてありません。
天孫族については、wikipediaでは、下のような記述があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%AD%AB%E6%97%8F
「天孫族は古代朝鮮半島北部の高句麗王族ないし扶余系民族に通じる種族と
する説がある。また高句麗や百済・新羅、あるいは渤海を建国した部族とも親近
関係にあったとされる。」
「また、これが『魏志倭人伝』に見える邪馬台国の前身たる部族国家(高天原)
で、このような原始国家を2世紀初頭前後頃から形成し、2世紀後半には分岐
国家の伊都国から神武天皇兄弟を輩出した。」
いずれにしても、先住民である出雲族も、その後に入って来た天孫族も、
朝鮮半島からの渡来系という話になりそうです。
もうひとつの渡来人集団、出雲族 - SOMoSOMo (hateblo.jp)
「斎藤氏は記紀神話に照らし合わせ、出雲地方の遺伝子を調べた上で、
「第13章 縄文と弥生をつなぐ古代出雲」
p258
出雲には、神宝といわれるほどのものがあった。 神宝を保有していたのは、朝廷では
なく出雲だったことは重要である。 つまり、出雲は神宝が置かれるか、集まってくる
ような場所だったのである。 朝廷はしきりにそれを調査したり、手に入れようとしている。
大量に出土した銅剣や銅鐸も、そのことと無関係ではないかもしれない。
==>> この神宝とはどんなものなのでしょうか。
https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E5%AE%9D-82549
「古代の神宝は『古語拾遺(しゅうい)』に、天富命(あめのとみのみこと)が種々
の神宝(かんだから)として鏡、玉、矛(ほこ)、盾(たて)、木綿(ゆう)、麻(あさ)
などをつくらしめたとあるように、祭祀(さいし)具とみられる。社殿が建てられ
ると、そこに祀(まつ)られる神の日常使用する調度品や什器(じゅうき)類、また
神殿を荘厳にするための用具などが納められ、これらをすべて神宝とよんだ。」
「〘名〙 (神の宝の意。古くは「かむたから」と表記。「かんだから」とも)
神の所有する財物。神の所有物。また、神へささげる品物。神社などへの奉納品。
しんぽう。
※書紀(720)崇神六〇年七月(熱田本訓)「天従(よ)り将(も)て来れる神宝
(カンタカラ)を、出雲大神(おほむかみ)の宮に蔵(をさ)む」」
p266
・・・縄文晩期には、島根県から山形県にいたる日本海沿岸地域はすべて縄文語が
話されていた。 このような裏日本語は、弥生前期ごろまで、山陰、北陸、信濃北部と
東北および関東の全域を占めていた。 ところが、弥生時代になって、大和政権が琵琶湖
を北上して若狭に進出したため、京都と兵庫の日本海側は弥生化した。 福井県、石川県、
島根県の一部もその影響を受けた。
なんと出雲には、縄文語の系統の方言が取り残されたように長く残っていた。だから、
縄文語直系の東北弁に似ているというのだ。
==>> 縄文語という名称は初耳ですので、こちらでチェックしておきます。
日本語は縄文時代に産まれた!?あの方言も「縄文語」の名残だった…。
https://www.youtube.com/watch?v=1jHdB3UipEk&t=179s
「縄文語の起源は縄文人が日本列島に移住した際に、元居た地域で使用して
いた言語が混ざりあって生まれたのだと推測されています。」
「事実、現代人のDNAを解析したところ、出雲出身者のDNAは
関東地方を飛ばして東北出身者のものと近いという結果も出ています」
このサイトでは、縄文語の復元研究もされていると述べています。
p272
出雲を宗教的な故地とする出雲文化圏のようなものが、私たちが想像するよりも早くから
列島には形成されていたのではないか、ということである。 それは呪術を共通の土台に
した宗教文化圏のようなものだったに違いない。
p273
「天つ神対国つ神」、「天的な宗教対呪術的な宗教」、「中央集権的な朝廷文化対地方的
な土着の文化」、このような対立構造のなかに、大和朝廷と出雲の関係がよくあらわれて
いる。
==>> このような宗教的なものがベースにあっての対立ということになると、
朝廷が出雲の神宝を調べて、手に入れたいと思ったのも、理解できるような
気がします。
出雲の権威の元である神宝を奪ってしまうということだったのかもしれません。
p278
邪馬台国時代になって、宗教形態も変化しつつあった。 銅剣・銅矛や銅鐸の伝統的
な弥生時代の祭りはすでに終わり、大きな墓と、鏡による新しい祭りの時代が始まって
いる。
この時期から、邪馬台国を中心とする近畿地方には、中国鏡がたくさん入ってくる。
p279
正始元年(240年)には、朝鮮半島の帯方郡から遣いが来訪し、黄金や金印、鏡
などを卑弥呼に与えている。
卑弥呼には中国の皇帝の権威がよほど必要になったらしい。
・・・238年、公孫氏はついに魏に滅ぼされ、帯方郡も魏の支配下に戻った。
卑弥呼が魏に朝貢したのは、まさに魏が公孫氏を滅ぼした翌年である。
==>> ここで言っている新しい宗教とは、どんな宗教だったのでしょうか。
卑弥呼の鬼道というのは有名ですが、それが力を失っている時期という
ことなのでしょうから、それが天孫族が持ち込んできた宗教という話なのか。
しかし、こちらのサイトでは、下のような記述があるので、鏡というものが
卑弥呼と大和朝廷を区別するものということは出来そうにありません。
古代の人々が「鏡」に感じた特別な意味
https://www.kokugakuin.ac.jp/article/150631
「時代が進む中で「当時の祭祀遺跡からは、本物の鏡だけでなく、鏡を模した
石製や土製の模造品も出現しました」と内川氏。また、古墳から出土した埴輪の
中には巫女の姿を表した「巫女埴輪」があるが、腰には呪具として鏡を付けてい
るものも見られ、祭祀と鏡との密接な関わりを想起させる。
今年5月に行われた天皇陛下の剣璽等承継の儀では、皇位と関係する「三種の
神器」が話題となった。剣・璽とともに鏡があり、長い日本の歴史の中で、鏡が
果たしてきた役割の大きさの一端が伺えるのではないだろうか。」
卑弥呼の時代の中国では、鏡と特定の宗教の関係はあったのでしょうか。
いろいろと検索してみたところ、こちらのサイトがヒットしました。
日本古代の鏡の信仰について
https://www.happycampus.co.jp/doc/640/
「鏡は神霊性を有すると考えられていた。特に道教においては、内篇『荘子』に
明鏡止水が道の体得者の象徴とされ、外篇『荘子』では鏡を聖人帝王の権力の
シンボルとしている。漢の時代、神仙思想が出現した影響で、鏡はこの世界の
政治的支配、帝王権力の支配として神秘化し神霊化した。魏・晋の時代に入ると、
深山幽谷に入って自ら道術を修める神仙術が盛んになり、鏡の呪力的な威力が
強調された。」
少なくとも、卑弥呼が朝貢した魏に関連しては、上記の神仙思想と「鏡の呪力
的な威力」という意味合いにおいては、これが卑弥呼の鬼道の下地にあった
のでしょうか。
しかし、鏡が大和朝廷の新しい宗教のシンボルという話になると、辻褄が
合いませんね。
こちらのサイトでは、卑弥呼の鬼道=神仙思想だとしています。
https://note.com/himiko239ru/n/nb6eff958fc6f
「卑弥呼の鬼道は神仙思想に基づく様々な方術(神仙方術)であり、卑弥呼は
その方術を駆使して人々に福を招き入れる方士であったと考えます。」
7、卑弥呼の鬼道と、魏の配慮
https://www.eonet.ne.jp/~temb/9/kagami/Sinzyukyo.htm#7
「卑弥呼は「鬼道に事え能く衆を惑わす。」と表され、帯方郡使、張政には同種
の信仰とみえた。」
「卑弥呼は越王の子孫なので(「中国・朝鮮史から見える日本2
」参照)、
卑弥呼の鬼道は、この越方そのものと思われる。呉越春秋は、越王勾踐が大夫種
の進言を容れて、東皇公、西王母を祭ったと記している。事実なら、これが越方
の始まりである。大夫種は楚人なので、楚から伝わったと考えて良いだろう。」
「制詔は卑弥呼に「特に汝に賜う」、「汝の好物を賜う」と記している。その特に
汝に賜れた好物の一つが鏡なのである。好物は「良い物」ではない。魏政府の
贈り物が良いのは当たり前で、わざわざ書くほどではない。「好む物」である。
卑弥呼は鬼道の術具となる鏡を喜ぶ。魏はそのことに配慮して、最もふさわしい
と思える鏡を作ったのである。」
・・・「卑弥呼は越王の子孫」などと書かれているので、それを調べてみたい
気持ちもあるのですが、読書が進まなくなるので、ギブアップします。
それにしても「越方」の意味が分かりません。越王勾践は、検索すれば出てくる
のですが・・・・
p283
卑弥呼の時代、すでに社会変化は起こりつつあった。 かつての銅鐸の祭りは集落単位
の地方的なものだが、鏡による祭りはより政治性が強く、全体を統合するような宗教だ。
それは支配者のための宗教である。
新しい連合社会に対応していくためには、呪術にすぐれた祭司王よりも、政治的で
世俗的な武力の王権が必要になり始める。
==>> 著者はここで、邪馬台国と力を競い始めた狗奴国(くぬこく/くなこく)との
戦いが激しくなって、中国の後ろ盾が必要だったと述べています。
しかし、卑弥呼の霊力では不足で、殺されたのかもしれないと推理して
います。
ここで、狗奴国と邪馬台国の関係に触れているこちらの動画をちょっと
みておきます。
この動画の作成者は九州説をとっていますのでご留意ください。
【ゆっくり日本史解説】魏志倭人伝『邪馬台国の滅亡まで』
https://www.youtube.com/watch?v=dAkCkNESEPo&t=560s
「邪馬台国の南には、強力な武器を持つ狗奴国(熊襲)がいて、
邪馬台国と狗奴国は敵対関係にあった。
「奈良の辺りには、大和朝廷の勢力がいて、大和朝廷の勢力は中国地方に
及び、九州に迫るほどの勢いがあった。」
「出土品などから日本最大の都市が、纏向遺跡だったことは確実・・・」
この動画では、大和朝廷が狗奴国を支援して、邪馬台国と戦ったことに
なっています。 また卑弥呼の最期は謎に包まれていることを述べていますし、
その後「中華は大混乱となり、邪馬台国を援助できるような状態ではなくなって
しまった」としています。
そして、「あくまで一つの説として、田油津媛が神功皇后に敗れた事で、
邪馬台国は完全に滅亡した。 350年頃に邪馬台国は滅亡した。」
とも述べています。
田油津媛については、こちらで:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%B2%B9%E6%B4%A5%E5%AA%9B
「『日本書紀』に記述される山門郡に居たとされる土蜘蛛の巫女女王。日本書紀
では仲哀9年3月丙申に神功皇后により誅殺されたとされるが、事実とすれば
4世紀半ば頃の出来事になる。」
p286
『梁書』にわずかに述べられているところによると、台与のあと倭国には男王が立ち、
中国の爵命を受けたという。 これが初期大和朝廷の誕生とみられる。 おそらく3世紀
末ごろ、邪馬台国から三輪王朝に変わったのである。
p287
百襲姫(ももそひめ)にのり移った大物主神の託宣には効果がなかった。
つまり、崇神天皇の時代には、まだ卑弥呼は生きていた。 しかし、彼女はやがて
大物主神と結婚し、奇妙な死に方をする。
ここに描かれた死には、やはり何か事件性があるのではないだろうか。
国内が混乱したとき、呪力と霊力の衰えた祭司王は殺される。
百襲姫の死の直後に「叛いたものは皆いなくなり、朝廷の支配に問題はなくなった」
という崇神天皇の発言がある。
崇神天皇はもともと三輪山の祭祀をめぐって、三輪山の神とギクシャクした関係が
あった。 また、大和朝廷のルーツを伝える神武の東征説話には、なぜか、女賊殺し
のモチーフが繰り返しあらわれてくる。
==>> ここでは、百襲姫(ももそひめ)=卑弥呼と著者が推理している中で、
卑弥呼が不可解な死に方をしたことが述べられています。
そして、それは崇神天皇の「謀略」だったのではないかと仄めかしています。
p293
国つ神から天つ神へ、スサノオからアマテラスへ、呪術的な蛇信仰から天的な太陽信仰
へ、これらはすべて統治のためのシステマチックな社会変化と対応している。
時代的、社会的な発展といえるのかもしれない。
だが、記紀の編者たちが推し広めようとした天照大神信仰は、万葉の人々にも、
もっとのちの時代の人々にも、ほとんど浸透しなかった。 この大神には、太陽神と
いう一面はあるにしても、あまりにも政治的・国家的な色彩が強いからである。
むしろ、人びとの暮らしのなかに根強く残っていくのは出雲の神々だった。
現代もなお、出雲の神々は人々のなかで生きている。
==>> なるほど、そういう結末の推理ですか。
「呪術的な蛇信仰から天的な太陽信仰へ」ということは十分に分かったの
ですが、上に書いた神仙思想や鏡との関係がいまだにすっきりしません。
卑弥呼の鬼道=呪術的な蛇信仰=鏡をつかう神仙思想という繋がりで
いいのか、あるいは、鏡を使う神仙思想は、大和朝廷の太陽信仰の
側なのかが、はっきりしないのです。
しかし、どちらにしても、大和朝廷は宗教的なものよりも、現実的、政治的、
武力的、国家的な力を優先させたのでしょうから、その宗教を自ら統制
できれば、なんでもよかったのかもしれません。
その政治的・国家的色彩が強いという意味においては、戦前・戦中の
神道の在り方と似たようなものだったのかもしれません。
現代の日本人が、万葉人のような感覚を持っているのかどうかは
分かりませんが・・・・
さて、これで、邪馬台国畿内説のミステリー作家が書いた本を読み終わりました。
いろいろ関連する言葉を調べていると、諸説いろいろあって、訳が分からなくなり
ますが、大変楽しく読むことができました。
今後も、出雲と大和、そして大和朝廷以前の、神道以前の神道、あるいは
アラハバキ神やミシャグジ神などに関する本をいくつか読んでみたくなりました。
===== 完 =====



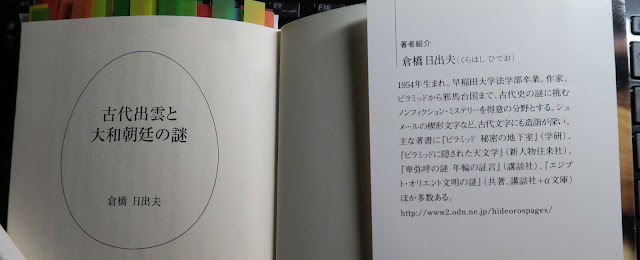



コメント
コメントを投稿