熊谷公男著「大王から天皇へ」を読む ―7(完)― 「乙巳の変」と「壬申の乱」 天武からが天皇だ 伊勢神宮はいつできた? 天武が作った日本と神話と現人神
熊谷公男著「大王から天皇へ」を読む ―7(完)― 「乙巳の変」と「壬申の乱」 天武からが天皇だ 伊勢神宮はいつできた? 天武が作った日本と神話と現人神
「第五章 律令国家への歩み」を読みましょう。
p249
カキの分割領有は、恣意的な収奪や中間搾取の温床となっていあ。 さらには、この
ようなタテ割り的支配体制は、・・・(国中の民の心は、氏族の別にこだわり、他族の
ものと対立し、それぞれ名(自己の氏族への帰属意識)に固執した)・・・とあるように、
人々の間に自己のウジへの強烈な帰属意識を生み出し、諸氏の構成員はたがいに対立感情、
対抗心をもつようになっていた。 ・・・排他的な同族意識を助長して、この支配体制
はしだいにうまく機能しなくなって、その歴史的使命を終えようとしていたのである。
==>> 「カキ」はその5に出てきました。
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2023/02/blog-post_64.html
「「カキ」とは、垣根のカキに通じ、区画するという意味で、ここでは諸氏族
によって区画され、囲い込まれた人間集団ということである。」
「カキ(民・民部・部曲などと書き、カキベ、カキノタミともいう)・・・」
・・・となっています。
p251
倭国では、蘇我蝦夷・入鹿父子の独裁体制が敷かれ、権力の私物化が進行していた。
これでは、風雲急を告げる半島情勢に迅速に対応することができないーーそのような
焦燥感が、中大兄皇子ら反蘇我氏派にクーデターの実行を決意させ、さらには支配層の
権力の一元化を核とした改新政権の諸政策の方向性を規定する要因の一つになったこと
はまちがいないであろう。
p254
皇極のかたわらでクーデターの一部始終をみていた古人大兄皇子(ふるひとのおおえの
みこ)は、「韓人が鞍作を殺した」と謎めいたことばを発して私邸に引きこもってしまった。
「三韓准調」の場で入鹿が殺されたことをいったのであろうか。
蘇我氏の私兵的存在であった東漢氏は軍陣を設けて戦う姿勢を示したが、高向国押
(たかむこのくにおし)の説得で断念する。 進退きわまった蝦夷は自邸で自刃した。
==>> この辺りのことは、wikipediaには以下のように掲載されています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E5%85%84%E7%9A%87%E5%AD%90
「645年6月、三韓から進貢の使者が来日し、宮中で儀式が行なわれた。
古人大兄皇子は皇極天皇の側に侍していたが、その儀式の最中、異母弟・中大兄
皇子(天智天皇)、中臣鎌子(藤原鎌足)らが蘇我入鹿を暗殺する事件が起きた。
古人大兄皇子は私宮(大市宮)へ逃げ帰り「韓人が入鹿を殺した。私は心が痛い」
(「韓人殺鞍作臣
吾心痛矣」)と言った。入鹿の父の蘇我蝦夷も自邸を焼いて
自殺して蘇我本家は滅び、古人大兄皇子は後ろ盾を失った(乙巳の変)」
「韓人が鞍作を殺した」「「三韓准調」の場で入鹿が殺された」というのは、
おそらくwikipediaのこちらの解説と関係ありそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%99%E5%B7%B3%E3%81%AE%E5%A4%89
「皇極天皇4年(645年)、三韓(新羅、百済、高句麗)から進貢(三国の調)
の使者が来日した。三国の調の儀式は朝廷で行われ、大臣の入鹿も必ず出席する。
中大兄皇子と鎌足はこれを好機として暗殺の実行を決める(『大織冠伝』には
三韓の使者の来日は入鹿をおびき寄せる偽りであったとされている)。」
・・・ただし、この本の著者は「謎」としていますので、謎なのでしょう。
p256
中大兄はすぐさま鎌足の考えに賛同し、・・・皇極はレガリアを軽皇子(かるのみこ)に授
けて譲位するが、軽は固辞して古人大兄を推した。 古人大兄は・・・辞退し、・・・剃髪
して・・・吉野に去っていった。
ここにいたって軽も固辞できなくなり、壇に昇って即位したという。
このときの譲位は、史上はじめてのものであった。
・・・これによって大王の生理的な死をまたずに王位を交代する道が開けたのである。
・・・譲位では、現大王がみずからの意志で次期大王にレガリアを授けるのである。
==>> この時までは、大王が死んだあとに、群臣が次期大王を認めて新大王が
即位するという慣例になっていたものが、ここで画期的な変更が行われた
ということだそうです。
ちなみに、レガリアとは「王権などを象徴し、それを持つことによって正統な王、
君主であると認めさせる象徴となる物品である。」とされています。
この時代には、まだ三種の神器はなかったのでしょうが、近年の天皇の
高齢化による譲位にも、このような歴史的背景があったわけですね。
ちなみに、三種の神器については、wikipediaでは、
「古代の日本において、鏡・剣・玉の三種の組み合わせは皇室特有のものでは
なく、「支配者」一般の象徴であったと考えられ、仲哀天皇の熊襲征伐の途次、
岡県主の熊鰐、伊都県主の五十迹手らは、それぞれ白銅鏡、八尺瓊、十握剣を
献上して恭順を表している。」
・・・とあるように、天皇家につながるものだけを示すものではないよう
です。
どの大王、天皇の時代から現在につながる神器が引き継がれているのでしょう。
p257
『書紀』によれば、新政権はまず「大化」という元号を建て、ついで矢つぎばやに
新しい施策を実施していった。
p259
大化改新の全体像は、律令国家が特定の政治的立場から編纂した『書紀』によってしか
研究することができないーーここに改新研究のむずかしさがある。
・・・問題の多い「改新の詔」はひとまず改新を考える史料からははぶき、より信憑性
の高い孝徳紀のほかの史料から改新の実態にせまっていくことにしたい。
乙巳(いっし)のクーデター後に結成された新政権の急務は、国内的には、さまざまな
弊害を生み出していた諸氏族によるカキの分割領有体制である部民制を解体し、それに
代わってすべての民を「公民(おおみたから)」として支配する一元的な支配体制を創出
することであり、対外的には、支配層の権力を一元的に集中して風雲急を告げてきた
半島情勢に即応できるような体制を作り上げることであった。
・・・これが「公地公民」制とよばれる支配体制の形成がめざされる歴史的要因であった。
==>> 改新の詔については、wikipediaにも以下の解説があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%96%B0%E3%81%AE%E8%A9%94
「この詔は『日本書紀』に掲載されている。従来はこれにより、公地公民制、
租庸調の税制、班田収授法などが確立したと考えられていた。しかし、藤原京
から出土した木簡により『日本書紀』に見える詔の内容は編者によって潤色され
たものであることが明らかになっている。」
「詔が実践できていない矛盾や事実もあり、これらが書紀の編纂者らによる潤色
であることは間違いないが、大化の改新は後世の律令制に至る端緒であった
可能性は高く、また大化年間だけにとどまらず以降の律令完成までの一連の
諸改革をいうとする解釈が近年は強い。」
ところで、「公民」を「おおみたから」と読むというのは、なんとなく素晴ら
しい響きなんですが、教科書的にはどんな説明になっているのでしょうか。
チェックしましたが「公地公民」とだけサラッと書いてあるだけでした。
そこで、こちらのサイトで確認しましょう。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%9C%B0%E5%85%AC%E6%B0%91-496535
「大和(やまと)国家は私地私民を原則として直轄領以外は諸豪族による国土の
間接支配を行い、世襲職制によってしだいに政治組織を整備していった
が、・・・・・・これは、中国の律令制度を導入して公地公民主義を採用し、
すべての土地(主として既耕の水田)と人民を国家の領有とするとともに、官僚
制による強力な中央集権体制を樹立しようとするものであり、・・・・・
公地と公民は律令の法文上では天皇の所有のような表現がとられているが、
現実には中央豪族(貴族)全体による共有とみるべきであり、
旧来の氏姓制体制下での彼らの諸特権は、いろいろな形で確保されている。」
・・・・つまり、私物化されていたものが、国有化されたってことなんで
しょうか。
p275
このような支配的イデオロギーを、臣下に喧伝(けんでん)し、浸透させる場が朝庭で
あった。 改新政権は、朝賀などの国家的な儀式や重要な法令の発布のたびに、臣下たち
を呼び集めて朝庭に整列させ、天つ神の“事依させ”を受けた大王だけが天下を統治できる
正統性をもっていることを宣り聞かせて、大王の隔絶した権威を繰り返し感得させた。
==>> “事依させ”はすでに見ましたが、ここでは「天つ神が命じる」という意味の
ようです。
前回その6で下のような話がありました。
「p237
倭王はすでに高句麗との修好以前から、国内では「治天下大王」と名のっており、
独自の「天下」観を保持していたことは否定しがたい。
アメキミの意味からみて、大王を天つ神の子孫とする「天孫思想」はすでに
芽生えていたことも確かであろう。
推古朝段階の倭王の王権思想は、天孫思想はすでに形成されていたが、その背景
にある王権神話はまだ記紀神話のように体系化はされていなかったので、倭王
と天や日の関係の説明に高句麗の王権思想を借用した、ということではなかっ
たろうか。」
推古朝にすでに天孫思想は芽生えていたようですから、この大化改新の
頃にはそれがかなり臣下に刷り込まれていったようです。
国津神vs天津神の神話の構想もかなり固まっていたのでしょうか。
p288
斉明天皇は、この広場の神聖な空間という性格は引き継ぎつつも、新たに須弥山像と
いう仏教施設を設け、装いを一新する。 須弥山像自体は仏教施設であるが、仏を
「蕃神」と観念し、天神地祇(てんしんちぎ)と仏教の守護神である諸天(帝釈天や
四天王)をいっしょくたに王権の守護神と考えていた当時の倭人の思考からすれば、
「廟塔(びょうとう)」(仏塔)のように高いと形容された須弥山像もまた、諸天の
住地であるばかりでなく、神々の依代とも考えられたとしてもいっこうに不思議でない。
==>> さて、ここで天神地祇とは「天の神と地の神。天つ神と国つ神」とされて
いますので、従来の神々が国つ神であったところに、天つ神という思想を
意図的に習合していったということなのでしょうか。
斉明天皇の在位は661年までになっています。
p292
581年(敏達十)、来朝した蝦夷の族長綾糟(あやかす)らは王宮である・・・・の
流れでみそぎをし、三輪山の方に向かって、王権への忠誠をその守護神である神々や
天皇霊(大王の祖霊)にかけて誓った。 これは服属儀礼の一部で、これ以前に、
蝦夷の調(貢ぎ物)の献上と、それに対する返礼の饗宴が行われたはずである。
このように、六世紀後半代には、蝦夷の服属儀礼は王宮の近傍の川原で行われて
いたが、その後、推古朝ごろからは場所を王宮の朝庭に移して行われる。
657年に倭京の造営にともなって飛鳥寺の西の広場が儀礼空間として整備されると、
その広場の須弥山像のもとが服属儀礼の場となる。
p293
これは大王の支配する「天下」的世界の究極の秩序の形成者が、天神地祇や天皇霊・
諸天などの王権の守護神であると考えられていたことを示している。
==>> この部分はなかなか興味深い内容があると思います。
伊勢神宮ではなく三輪山が出てきているからです。
Wikipediaによれば、伊勢神宮の創設時期は諸説あって、
「伊勢神宮創祀年の主な説としては、垂仁朝説、5世紀後半の雄略朝説、6世紀
前半の継体もしくは欽明朝説、6世紀後半の用明・推古朝説、7世紀後半の天武・
持統朝説、7世紀末の文武朝説などが挙げられる。」
・・・となっています。
上記の説明では、581年に三輪山の方に向かって・・・と書いてありますから、
おそらくその時期にはまだ伊勢神宮はなかったのではないかと憶測します。
つまり、7世紀説が近いのではないかということです。
三輪山・大神神社は国津神系だと思いますので、天津神系である伊勢神宮は
まだ過渡期だったのではないかと妄想するわけです。
そして、この話は、先に読んだこの本では、下のような記述がありました。
村井康彦著「出雲と大和」
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
「p136
『日本書紀』垂仁天皇二十五年三月の記述によると、「天照大神を豊耜(鍬)
入姫命(とよすきいりひめのみこと)から離し、その奉祭を倭姫命に託した。
・・・伊勢の国に到った時、天照大神が「この神風の伊勢国は美しい国だから
ここに居たい」と教示なさったので、その祠を伊勢国に建て、斎宮を五十鈴川の
ほとりにたてられた」とある。・・・こうして天照大神=鏡は伊勢の地に祭られ、
これが伊勢神宮の創始となった。」
・・・ただし、垂仁(すいにん)天皇については、wikipediaでは
「考古学上、実在したとすれば3世紀後半から4世紀前半ごろの大王と推定
されるが、定かではない。」
となっていますので、上記のストーリーとは大きく異なるようです。
p297
重祚した女帝斉明の二大「興事」である“石の王都”倭京の建設と北方遠征は、須弥山像
を中心とした飛鳥寺西の儀礼空間を媒介に結び付くことがわかっていただけたのでは
ないかと思う。 “石の王都”の建設は、これまでにないやり方での「天下」的世界の
中心の荘厳であり、北方遠征は「天下」的世界の拡大策ということができる。
==>> この斉明天皇の古墳などについての動画がありましたので、
こちらで見ておきましょう。
世界の墳丘から410「斉明天皇の驚愕〜牽牛子塚古墳〜」
https://www.youtube.com/watch?v=onGu899rQq0&t=371s
斉明天皇の大規模な工事は不評だったようです。
p307
斉明女帝の死と白村江の敗戦によって、王都の荘厳と「天下」的世界の拡大を基調とした
斉明朝の特異な路線は、完全に雲散霧消してしまう。 唐軍に惨敗を喫した倭国は、一転
して国土の防衛体制の強化に躍起となる。 敗戦の翌年の664年(天智3)には、対馬・
壱岐・筑紫などに防人(さきもり)・烽(とぶひ)を置き、筑紫に水城(みずき)を築いた。
p308
665年には、百済の亡命貴族に命じて大宰府の北と南に大野・椽(き)(基肄(きい))
の二城を、長門にも一城を築かせた。 いわゆる朝鮮式山城である。
p317
即位した天智天皇は、その二年後の670年、全国的規模で戸籍を作成する。
その時の干支によって庚午年籍(こうごねんじゃく)とよばれる。 わが国最古の
戸籍である。
p318
このような造籍作業をはじめて全国的規模で行うことは、想像以上に大変なことであった。
そもそも列島の一般の民衆には、本来、姓がなかった。 しかし奈良時代には、天皇と
奴婢を除いて、すべての人々が姓を有している。 一般公民は「〇〇部」という形式の
部姓がふつうである。
・・・一般の民衆の多くには、以前の部民制の所属関係にもとづいて部姓が与えられたと
考えられる。
==>> この姓がいつからあるのかという点に関しては、その3で下のような
記述がありました。
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2023/02/blog-post_6.html
「「埼玉県行田(ぎょうだ)市の稲荷山古墳出土鉄剣銘に記された辛亥年(471年)
当時の大王。」
「p118
鉄剣銘の系譜には、のちの氏族系譜とは大きく異なる点もある。それはウジ名
(姓)が記されていないことである。船山古墳の銘文大刀を作ったムリテという
人物も、名前だけで姓がない。これは、オワケ臣の時代にはまだ一般にウジ名が
成立していなかったことを示す重要な証拠となる。
これまで五世紀の豪族を、葛城・和珥・吉備・上毛野などと、氏族名でよんで
きたが、正確には、それらの氏族の先祖、あるいは原葛城氏などというべきなの
である。鉄剣銘は、ウジ名の成立に先立って氏族系譜が存在していたことを示し
ている。」
・・・つまり、少なくとも471年当時には、豪族であっても氏族の姓が
なかったということです。
そして、この戸籍が作られたのが670年という話です。
奈良時代は710年からですから、この670年から40年ぐらいかけて
姓が広まっていったようです。
p328
大海人は川のほとりではるか南の伊勢神宮の方角を向き、天照大神を遥拝する。
戦勝祈願であろう。・・・・吉野を発ってわずか四日で、大海人方の戦闘態勢の基礎
が固まったのである。
==>> これは壬申の乱の話の一部です。
壬申の乱と伊賀!!大海人皇子(天武天皇)の逃避行!!
https://www.youtube.com/watch?v=IH_rQJqhwv0&t=91s
私の興味は、伊勢神宮にあります。
671年に壬申の乱がおこり、その時に、上記のように伊勢神宮の
天照大神を遥拝したとなっています。
p293で581年には伊勢神宮はまだなかったらしいと推測しましたが、
この671年にはあったようです。
この110年の間に、アマテラスの天津神の体制が出来上がってきたと
考えていいのでしょうか。
「エピローグ 天皇の出現」
p334
壬申の乱は、貴族から民衆まで、多くの人々を巻き込んだ古代史上最大の内乱であった。
ほとんど丸腰で反乱に立ち上がった大海人皇子が、的確な状況判断と迅速な行動で
短時日のうちに軍事的優位にたち、ついには近江朝廷を打倒したことに、人々は
ただただ驚嘆したに違いない。
p335
乱後、天武(大海人)は“神”とあがめられる存在になっていたのである。
天皇号の成立時期については、一部に推古朝説もあるが、現在は、筆者も含めて
天武・持統朝説をとる研究者が多数を占める。
筆者は、「天皇」という称号は、まず天武天皇をさす尊称として天武朝に誕生し、
没後の持統朝に浄御原令の制定とともに君主号として法制化されたと思う。
==>> 上からの話の流れでいうならば、 671年に壬申の乱がおこり、
その際に伊勢神宮はあり、天武になってから天皇という称号ができた
ということであるならば、天津神の神話を作り出すという意味においても
タイミングがいいかなと感じます。
p338
「天皇」の語は、中国の道教の重要な神で、北極星を神格化した「天皇大帝(てんこう
たいてい)」に由来するとみるのが定説である。
p339
「天皇」の和訓は「スメラミコト」といい、宣命(せんみょう)など、口頭で天皇を
よぶときは、この和訓がもちいられた。
スメラミコトのスメラは・・・・「澄む」に由来し、スメラミコトは政治的・宗教的
に聖別された神的超越性をいいあらわす特殊な尊称として王権が定立したとみるのが
正しいと思う。
『万葉集』ではオオキミが天皇をさす語として頻用されているのに、スメラミコトは一度も
用いられていない。 それは、オオキミが日常語であるのに対して、スメラミコトは
生活次元とは隔絶した、王権の国家的な儀式などでもちいられる特殊な新造語だった
ために、生活感情を表現する歌にはなじまなかったのである。
p340
要するに、「天皇」という二文字に込められた理念は、天つ神の系譜をひく“神”で、
皇帝に準じる格をもった君主ということになる。
p340
天武は、未婚の王女を大王(天皇)の名代として天照大神に奉仕させる斎宮(いつきの
みや)の制度を復活させ、娘の大伯皇女(おおくのおうじょ)を伊勢に遣わす。
皇祖神天照大神を祭る神社として伊勢神宮の地位がにわかに上昇するのである。
これと密接に関係するのが、王権神話の体系化の推進である。
p341
天武朝には、「天皇」号ばかりでなく、「日本」という国号も定められる。
==>> はい、ここで私が知りたかったところが繋がってでてきました。
特に、伊勢神宮の創設・地位の充実と、神話の体系化です。
この大海人皇子=天武天皇がキーパースンだったんですね。
p347
最後に筆者が強調しておきたいことは、列島の君主は決して太古の昔から“神”で
あったのではない、ということである。
壬申の乱に勝利し、人々から「大王は神にしませば」とあがめられた強烈な神的
権威の持ち主であった天武こそが、現神「天皇」と「日本」の生みの親であった。
==>> 現人神(あらひとがみ)は昔よく聞いた言葉ですが、ここでは
現神と書いてあります。
Wikipediaによれば、「現御神、現つ御神、現神、現つ神、明神とも言う
(読みは全て「あきつみかみ」又は「あきつかみ」のどちらかである。)。」
となっています。
やっと、この本を読み終わりました。
いくつかの疑問が解けたので、かなりすっきりしています。
もちろん、古代史には諸説紛々というのがついてまわりますから、じれったい部分は
あるのですが、個人的にかなり納得できて満足しています。
今後は、この天皇、神話、神社、天津神などよりも前の時代に関して、何冊か
読んでいきたいと思っています。
その感想文は、フィリピンのバギオ市でボチボチと書くことになりそうです。
===== 完 =====
===============================
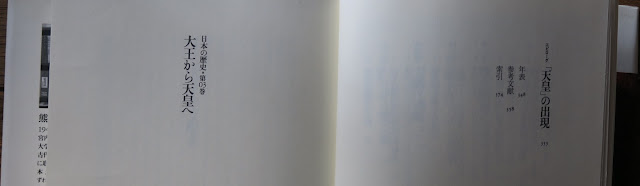




コメント
コメントを投稿