武光誠著「古代日本誕生の謎」を読む ―2― 太陽神を祭らせ、朝廷の祭祀を拡充し、大王家の系譜や神話を整理、 天神と国神の神話のわけ
武光誠著「古代日本誕生の謎」を読む ―2― 太陽神を祭らせ、朝廷の祭祀を拡充し、大王家の系譜や神話を整理、 天神と国神の神話のわけ
「第二章 戦乱時代の勝者」に入ります。
p118
大和朝廷は、四世紀から七世紀に至る約400年間をかかて、北海道、東北地方と
九州南端を除く日本列島の大部分の統一に成功した。
その時期に、青銅器の分布の中心が、北九州から近畿地方に移っているのだ。
・・・銅鏡と刀剣類から成る新たな宝器が「大和」を軸に広まっていく。
p120
五世紀初頭に、朝廷は朝鮮経営に便利な河内に本拠地を移した。それは、大阪平野
の大規模な開発によって可能になったとされる。 朝鮮半島産の鉄が、そのような開拓を
促進した。 この時期の地方豪族で、朝廷から鉄を分与されるために前方後円墳を作り
始めて大王の配下に入った者も多かったと思われる。
全長486メートルの仁徳陵古墳を作るために必要な土砂の量は、140万立方メートル
にも及ぶ。 人力だけでそれを築くためには、延べ約540万人の労力が必要だ。
驚くべき数字だ。
==>> 昔はじっくりゆっくり時間と労力を掛けて国造りをやっていたんですねえ。
それにしても、延べ540万人ってことは、仮に1年300日で計算すると
18,000人/日ですね。 1,800人で仕事をしたとすれば、10年
掛かりますね。
こちらのサイトに崇神天皇の時(589年)の日本の人口が
総数393万人、男91万人、女302万人となっています。
まあ、これは日本全土での人口ですから、奈良盆地周辺でどれくらいの
労働人口があったのかは分かりませんが、ひとつの集落あたりの人口が
1, 000~2,000人ぐらいだとすれば、1,800人は当たらずとも
遠からずかもしれません。
こちらのサイトに非常に面白い推定値がありました。
大林組による計算結果です。
現代技術と古代技術による仁徳天皇陵の建設
https://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi/detail/kikan_20_idea.html
「この工事のピーク時には1日に2,000人も作業していた。さらに現場で働く
人びとのために、膨大な数のスキやクワなどを作る人員、さらに管理や再生産の
ためには、集団によるシステムも必要であり、専門技術の指導者なども含めると、
ここには総勢3,000人もの人びとが常駐したと想定される。
そればかりではない。この大集団に食事なども支給されなければならない。3,000
人に毎日食事を用意する"後備え"には、陵を造る直接の労働力とは別個にほぼ同
数の要員が必要である。すなわち、この場所に一時に6,000人もが集中したこと
にも気付きたい。」
p123
武烈天皇の没後、仁徳天皇の血を引く男性のめぼしい王族がいなくなった。
そのため、その時期の朝廷の最有力者であった大伴氏と物部氏は、応神天皇の五代目
の子孫という傍系だが、越前にいて大勢力をもつ王族、男大迹王(おおとのみこ)(継体
天皇)を迎えて大王の位につけた。 そして、継体天皇の下で、急速に中央集権化が進んで
いった。
p124
さらに、六世紀中葉の欽明天皇の時に大王の権威が急激に高まった。王女に太陽神を
祭らせる慣行を作り、朝廷の祭祀を拡充し、大王家の系譜や神話を整理したのだ。
その時期には、蘇我氏が急成長している。
==>> なるほど、この欽明天皇の頃に、天照大神の太陽神や、神話が整理された
ということのようですね。
欽明天皇は509~571年の人だそうで、古事記の編纂は712年となって
いますから、およそ140年ぐらい前には、神話や天皇家の系譜を準備して
いたことになりますね。
つまり、神道の基礎が作られたのは、欽明天皇の時代ということなので
しょうか。
「王女に太陽神を祭らせる慣行」というのが斎王のことを言っていると
すれば、こちらのサイトでは、すでに崇神天皇の頃に始まっていますね。
制度として始めたのが欽明天皇だったということなんでしょうか。
本一覧は、歴代の斎王の名前と在任期間、天皇と斎王の血縁関係、伊勢斎宮への
群行の有無などをあらわしています。
https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/50382036203.htm
こちらのサイトによれば、正式な制度としては、天武天皇の時のようです。
斎宮(さいぐう/さいくう/いつきのみや/いわいのみや)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E5%AE%AE
「斎王は天皇の代替わり毎に置かれて天照大神の「御杖代(みつえしろ、神の意
を受ける依代)」として伊勢神宮に奉仕したという。ただし史料上は必ず置かれ
たかどうかは不明で、任期などもそれほど明確ではない。用明天皇朝を契機に
一時途絶えたが、天武天皇の時代に正式に制度として確立し(『扶桑略記』は
天武天皇が壬申の乱の戦勝祈願の礼として伊勢神宮に自らの皇女大来皇女を
捧げたのが初代とする)、以後は天皇の代替わり毎に必ず新しい斎王が選ばれ、
南北朝時代まで続く制度となった。」
p125
七世紀初頭に、聖徳太子と蘇我氏が積極策をとり、大きな成果を上げた。
高句麗、新羅に対する強硬的外交と遣隋使の派遣とで日本の国際的地位を高め、・・・・
大陸風の寺院建築が始まり、・・・本格的な仏典研究がなされ・・・・
p141
大和朝廷は、服属した豪族の祖先を大王の系譜に取り込んで発展していったのだ。
桃太郎伝説は、吉備津彦神社が伝える吉備津彦の事跡をもとに作られている。
吉備氏は、早くから自家を大王の下で鬼、すなわち王権に従わぬ者共を討った英雄の子孫
と位置づけていたのだ。
大和朝廷は、吉備の地方文化を多く採り入れている。 製塩と製鉄はその代表的な
ものだ。
日本人は長い間、朝鮮半島から鉄を輸入していたが、五世紀初頭の吉備でようやく
製鉄が始まった。
p142
高度な技術をもつ吉備氏の巨大古墳は、次のように物語る。
「大和朝廷は俺のところから分かれた新興勢力だから、俺たちは大王と同等の古墳を作る
のだ」
しかし、権勢を誇った吉備氏は、五世紀末に凋落の運命をたどった。
==>> 今の時代も同じようなものかもしれませんが、他国の最先端の文化である
仏教や、最先端の技術である製鉄や製塩を押さえることが、日本列島の
中で、勢力を拡大できるかどうかのポイントだったんですね。
それと並行して、神道の面からみれば、大王から天皇へとつながる系譜を
積み上げていったという、権威の作り込みが進められたということでしょうか。
p146
三世紀には邪馬台国が中国の魏、晋(西晋)の王朝との交流をもった。
そこで、全国政権となるために大和朝廷は、大陸から伝わった高度な文化をもつ北九州
を押さえねばならなかった。 320年代に大和朝廷の攻撃を受けると、そこを治めて
いた邪馬台国は、案外もろく崩壊した。
その時から、文化の中心が奈良盆地に移った。
p147
中国と通交した卑弥呼の都が、本当に纏向遺跡のような中国産の遺物のないものだろうか。
あるいは、遺跡の三発掘の部分に大量の二世紀末から三世紀初頭の中国鏡が埋まっている
のだろうか。
==>> 著者は、邪馬台国九州説を採っていますので、このようなストーリーに
なるようです。
p151
佐賀県神埼町吉野ケ里遺跡の全盛期も、一世紀中葉だ。・・・『魏志倭人伝』に出てくる
弥奴国(みなこく)の跡だと考えられる。
巨大な墳丘墓が、吉野ケ里にある。 戦闘で傷ついた戦士の骨も、そこから出土した。
それによって弥奴国の人びとが、交易圏をめぐって奴国(なこく)等としきりに争った
ありさまがわかる。
一世紀末に、奴国の西方の糸島平野にあった伊都国(いとこく)が強大化し始めた。
そして、そこの首長の帥升(すいしょう)は、玄界灘の小国をまとめ、「倭国王」と自称
して朝貢した。 107年のことだ。
p153
邪馬台国は一世紀中葉頃起こり、二世紀初頭の弥奴国(みなこく)の衰退をきっかけに
強大化して、筑後の盟主になっていった。
中国の史書は、107年の帥升の遣使のあと7、80年間、平和な時代が続いたという。
そして光和年間(178―84)に、倭国に大乱が起こった。 その後に、卑弥呼が女王
に立ってそれを治めたと伝える。
邪馬台国が伊都国に大率(だいそつ)という役人を置き、外交や交易の監督をさせている
と記す。
==>> これは、著者の邪馬台国九州説に基づいたストーリーです。
私は、長崎県出身なので、この説を応援します。
今は、埼玉県在住なので、埼玉県説がでたら、それを応援します。あははは
先日、テレビで、邪馬台国がどこにあったのかという専門家たちのサミット
がありました。 その時に、ある専門家が、「邪馬台国は絶対にここにあった」
などと主張する人がいたら、それは本当の専門家ではないということを
言っていました。 つまり、明日何が見つかるかは誰にも分からず、それに
よって、今までの定説なるものがひっくり返る可能性が常にあるからだ
という話でした。 ごもっともです。
p156
・・・卑弥呼の時代の銘をもつ三角縁神獣鏡が多い。 そこで、それを魏が卑弥呼に
与えた銅鏡だとする説が出されたこともある。
ところが、中国の王仲殊(おうちゅうしゅ)氏がそのような意見に対する批判を
出している。 ・・・三角縁神獣鏡に似た意匠の鏡は中国にはなく、そのような大型の
鏡も見られない。 だから、それは日本で新たに創られたものだ。 三角縁神獣鏡に
多少似た意匠をもつ鏡は、江南を押さえ魏と対立した呉にある。 だから、呉の工人が
日本に移住して三角縁神獣鏡を作ったと王仲殊氏はいう。
==>> 稲作文化を携えて九州にやってきたのは江南の人びとだという話は、
先に読んだ本の中にも出てきました。
アニメ「キングダム」の戦乱の時代に、北から圧迫された呉を含む江南の
人々が九州に避難してきたという筋書きです。
安本美典著「日本民族の誕生 ― 邪馬台国と日本神話の謎」を読む
― 揚子江流域から戦火を逃れて稲作と共にやってきた倭人?
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/blog-post_10.html
「p187
日本の文化も、言語も、ともに、朝鮮半島からその北方へとつながる要素と、
中国の揚子江(長江)流域からその西や南への延長上へとつながる南方的な要素
とをもつ。
弥生時代の初めにかけて、中国の揚子江(長江)下流地域から、ビルマ系言語を
使う人々を主とする人々が、稲作文化をたずさえてやってきて、「原倭人」と
混交し、「倭人」が成立した。」
「p212
稲作が、江南から直接日本、特に九州地方へ渡来したとする説は、多くの農学者
も支持するところである。 ・・・・日本の水稲に最も近似する品種は(朝鮮
半島のものよりも)華中のジャポニカの一群であることなどが証明されている。
・・・朝鮮半島を経由したとする考えは、考古学者のなかに支持の多い説といわ
れている。しかし、陸路を揚子江流域から遼東半島に至って鴨緑江を渡り、文字
通りに半島を南下したとは、農学者や植物学者にとっては容易に賛同し難い
推理であろう。 遼東半島付近は北緯40度、盛岡よりも北である。」
p158
邪馬台国九州説は、二個の立場に分かれる。 邪馬台国が東方に勢力を伸ばしてやがて
大和朝廷になったとする説と、邪馬台国は大和朝廷に併合されたという意見だ。
前者は、「邪馬台国東遷説」と呼ばれる。
ところが、纏向遺跡が220年頃に作られたことが明らかになったために、東遷説は
ほとんど成り立たなくなった。
卑弥呼と同時代の纏向遺跡は、邪馬台国ではありえない。
p159
朝廷と縁が深い宗像神社や、宇佐八幡宮は、邪馬台国と対立した豪族が祭ったものだ。
宗像神社は、朝廷支配下の航海民(海部あまべ)が祭ったもので、・・・古代には沖ノ島の
沖津宮が最も重んじられていた。
p161
宇佐八幡宮は、・・・古文書を見ると、かつては宗像三神がそこの主な祭神であったことが
わかる。 このことは、宇佐の首長が宗像から移住した航海民であったことを示す。
朝廷はしばしば宇佐にも豪華な供え物をしている。
==>> 著者は基本的に邪馬台国九州説に基づいた話をしているので、
ここで、その説の全体像をこちらのサイトで見ておきましょう。
「諸説あり」邪馬台国は九州にあった(中国の学者説)
https://www.youtube.com/watch?v=mhf9qR6fwUc&t=116s
・・・この動画でみると、九州にあった邪馬台国が、地名と一緒に畿内へ
移動したという東遷説を信じたくなりますね。
もうひとつ、日本国内での議論に基づいた九州説の動画を見てみましょう。
邪馬台国は九州のあの県だったという説に説得力があったので~
九州説、畿内説どっち?
https://www.youtube.com/watch?v=RRKlrKeNU9Y&t=61s
・・・なんと、邪馬台国は宇佐市にあったという説です。
宇佐神宮や宇佐八幡宮との絡みで・・・・
こちらの動画では、九州説と畿内説の論争の中で、九州説が次第に分が悪く
なってきたことを語っています。
かなりのマニアじゃないと分からない内容ですが、素人の私にも雰囲気だけは
分かりました。
結局、考古学における年代測定の方法にいろいろと問題があったことが
話をややこしくしてきたようです。
邪馬台国九州説衰亡史
https://www.youtube.com/watch?v=Xtu2rcoscIQ&t=178s
「近年における邪馬台国九州説衰退の歴史を吉野ヶ里ブームから遡ってみま
した。ただし、この動画の作者が九州説のため、それは違うぞといった見解に
なっています。物の味方はいろいろあるということで、その点はご容赦を!」
p163
箸墓古墳の発生は、大和朝廷の首長霊信仰を確立させた画期的出来事だが、宇佐の首長
はそのわずか30年後に新たな信仰を取り入れたのだ。 それをきっかけに、豊前・豊後
と大和朝廷との密接なつながりが始まった。
p164
大和朝廷は、吉備の首長の協力のもとに水軍を編成して北九州に攻め寄せたのだろう。
豊前、豊後の諸豪族の水軍が、それに協力した。
彼らは、福岡平野の豪族を従えて、原口古墳、津生生掛(つしょうおいかけ)古墳を
作った豪族の先導で邪馬台国に攻めかかった。
==>> これで、邪馬台国・卑弥呼の鬼道、精霊信仰が、大和朝廷の首長霊信仰の
集団に敗れたということのようです。
ここで、ちょっと宇佐八幡宮を確認しておきましょう。
http://www.usajinguu.com/lineage/
「宇佐の地は畿内や出雲と同様に早くから開けたところで、神代に比売大神が
宇佐嶋にご降臨されたと『日本書紀』に記されています。比売大神様は八幡さま
が現われる以前の古い神、地主神として祀られ崇敬されてきました。八幡神が祀
られた8年後の733年(天平5年)に神託により二之御殿が造立され、宇佐の
国造は、比売大神をお祀りしました。」
「八幡信仰とは、応神天皇のご聖徳を八幡神として称(たた)え奉るとともに、
仏教文化と、我が国固有の神道を習合したものとも考えられています。」
・・・宇佐神宮のご祭神は、応神天皇と神功皇后、そして、比売大神と
なっています。 この比売大神とはどんな神さまなのかをチェックして
おきましょう。
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%A5%9E%E5%AE%AE-34450
「宇佐神宮【うさじんぐう】
大分県宇佐市南宇佐に鎮座。宇佐八幡宮とも。旧官幣大社。応神天皇,
比売(ひめ)神(地主神),神功皇后をまつる。欽明天皇の時の鎮座と伝える。
古来より朝廷の崇敬をうけ,奈良時代には鎮護国家の神として信仰を集めた。」
・・・これによれば、比売神は「地主神」ということですから、
いわゆる客人(まろうど)神とかアラハバキ神とされる神なのかもしれません。
こちらのサイトでは、少し違った説明があります。
「八幡社では比売大神を祀る。総本宮である宇佐神宮(大分県宇佐市)や宇佐
から勧請した石清水八幡宮(京都府八幡市)などでは、宗像三女神を祭神として
祀る。しかし、八幡社の比売大神の正体については諸説があり地域によっても
異なる。」
p169
四世紀の北九州に、朝鮮半島の陶質土器が輸入されている。それは、やや硬質の須恵器風
の土器だ。 五世紀初頭には、福岡県筑前町小隈窯趾(おぐまようし)や同山隈(やま
ぐま)窯趾で、朝鮮半島の伽耶土器にならった須恵器の生産が始まった。
こういった新技術は、すぐさま大和に入って各地に広まっていった。
==>> ここで、須恵器の話が出てきたのですが、先に読んだ本の中でも、
須恵器と出雲そして大和朝廷との関係を述べている部分がありました。
岡谷公二著「神社の起源と古代朝鮮」を読む ―
新羅=出雲=邪馬台国vs大和朝廷? 宇佐八幡vs大和朝廷?
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/09/blog-post_30.html
「p159
大和朝廷は神々の世界の事柄に関しては、出雲に一歩も二歩も譲るところが
あったからである。このような怖れの背後には、政治的に支配したあとでも、
出雲そのものに対する怖れがあったように思われる。
出雲には早くから新羅・伽耶の人々が入り込み、鉄産業、須恵器から医薬に至る
までの、いわば先進文化の一つの根拠地であった。 因みに、出雲は「後々まで
呪い(まじない)とか薬の発達した地域であり、中世以後大都市となった奈良や
京都では、出雲から来た薬屋が多かった」と門脇禎二氏は言う。
p160
大和朝廷の出雲への怖れは、やや後の、古代豊前地方にあったとされる、
宇佐八幡を中心とした「秦王国」の先進文化圏への怖れとよく似ている。
かつて豊国と呼ばれた地域に、朝鮮半島から秦氏系の人々が多く移り住み、
宇佐八幡を中心として、「秦王国」ともいうべき文化圏を作り出していた・・・・
大田田根子に話を戻すならば、祀る人が渡来系でなければならないとするなら、
祀られる神もまた渡来系なのではあるまいか?
・・・・大物主は神統からいって渡来系である。」
・・・これを読む限りは、須恵器は日本海側の出雲などに最初に入ってきたと
読めるのですが、今読んでいるこの本では、五世紀初頭に筑前町で生産が
始まったとしているわけですね。
そこで、どちらが早かったのかを調べてみたのですが、
こちらの須恵器の解説の中には、以下のような部分があります。
https://kotobank.jp/word/%E9%A0%88%E6%81%B5%E5%99%A8-83326
「文献史料からは『日本書紀』垂仁(すいにん)天皇3年の一云条に「近江国
(おうみのくに)鏡(かがみ)村の谷の陶人(すえびと)は則(すなわ)ち天日槍
(あめのひぼこ)の従人(つかいびと)なり」とある。さらに雄略(ゆうりゃく)天皇
7年是歳(ことし)条には「新漢陶部高貴(いまきのあやのすえつくりこうき)」の
名がみえる。前者は滋賀県蒲生(がもう)郡竜王町所在の鏡窯址(ようし)群を示す
ものと考えられるが、古くさかのぼる須恵器窯址は確認されていない。後者の
故地は不明であり、両記事ともあいまいな点が多く、確たるものとはなりえ
ない。」
・・・確たるものとはなりえないとありますが、仮にこれが事実だったと
したら、垂仁天皇は3世紀後半から4世紀前半ごろの大王と推定されている
そうですから、筑前町よりも近江国の方が早かったということになりそうです。
p172
出雲の文化は、一世紀中葉以来、急速に進展した。 古代の出雲は日本海沿岸の航路の
中心になっていたからである。
p178
日本海航路と陸路を用いた出雲から大和に至る広い範囲の交易が盛んだったありあさまが
わかる。
大和朝廷成立以前の大和や河内の人びとは、二世紀中葉から末にかけて当時先進地で
あった出雲から多様な文化を受容したのであろう。 そして、そこに吉備の文化をもつ
移住者が来て大和朝廷を起こした。
p186
大国主命が天照大神の子孫に地上の支配を差し出す国譲りの神話は、六世紀中葉頃に
整えられたものだ。 それは、大王の祖先とされる首長霊信仰に基づく天神(あまつかみ)
を、祖霊信仰による国神の上に位置づけるために作られた。
かつて出雲に有力な文化圏があったとする記憶があったので、大国主命が国神の代表と
されたのだ。
==>> この部分では、 出雲、吉備と奈良の大和朝廷との関係を述べていますが、
合わせて、その神話のストーリーが、首長霊信仰・天皇信仰を推し進める
大和朝廷側が天照大神を頂点とする天神を最高神として、出雲・吉備などを
その下で働く国神、つまり祖霊信仰あるいは精霊信仰の集団だと位置づける
支配の道具立てとしたようです。
まあ、それにしても、壮大な道具立てですね。
どんなグループがこういうものをプロデュースしたのか、その顔が見てみたい
気がします。
これで、第二章を終わりました。
次回は、「第三章 東北の歴史が語るもの」を読んでいきましょう。
===== 次回その3 に続きます =====
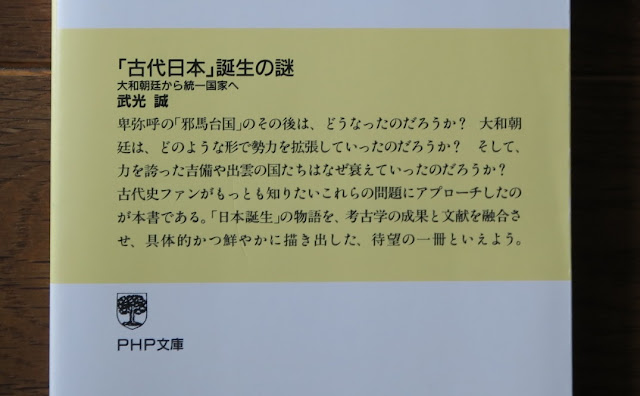
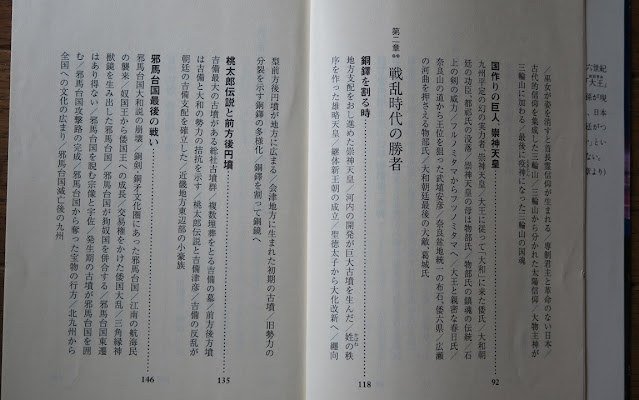





コメント
コメントを投稿