金澤正由樹著「古代史サイエンス ― DNAとAIから縄文人、邪馬台国、日本書紀、万世一系の謎に迫る」を読む ― 後編
<<前編からの続きです>>
p195
さて、宇佐神宮は、応神天皇と神功皇后、そして比売大神が祭神です。
これから宗教的に判断すると、「皇統断絶」が疑われている継体天皇
の子孫である天武天皇は、外部の人間ではなく、神武天皇からつながる
男系ということになります。
==>> 継体天皇については、過去に読んだ本の中に下のような
解説がありました。
熊谷公男著「大王から天皇へ」を読む ―4― 継体天皇は婿入り?
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2023/02/blog-post_8.html
「p134
記紀によれば、雄略の後の大王は清寧(せいねい)―顕宗(けんぞう)―
仁賢(にんけん)―武烈(ぶれつ)と続くが、いずれも短命に終わる。
六世紀は、継体天皇の異例づくめの即位とともに開幕する。
金村は物部麁鹿火(もののべのあらかい)大連らとはかって、
応神天皇の五世の孫の男大迹(おおど)王を越の三国(福井県三国町)
から迎えたという。 これが継体天皇である。
p196
宇佐神宮の祭神には、「比売大神」という女神もいるのですが、
具体的に誰なのかわからないようです。
普通の神社は拍手は2回ですが、宇佐神宮では出雲大社と同じく
4拍手です。神道的には、4は「死」に通じるので、誰かの
霊を閉じ込めていることになるそうです。
井沢元彦氏によると、台与の後継者かもしれないとのこと
ですが・・・・・
==>> wikipediaによれば、下のようになっています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E5%A3%B2%E7%A5%9E
「八幡社では比売大神を祀る。総本宮である宇佐神宮
(大分県宇佐市)や宇佐から勧請した石清水八幡宮
(京都府八幡市)などでは、宗像三女神を祭神として祀る。」
ここでは、「台与の後継者」かもしれないという説が
紹介されていますが、前回読んだ本の中では
北九州の邪馬台国連合の巫女たちではなかったかと
推定していました。
p199
現在の皇室は、かつては傍系だった光格天皇の直系の子孫です。
光格天皇は、前天皇の後桃園天皇の末期養子なのですが、皇后には
前天皇の第一皇女をもらっています。
末期養子というのは、当主に子がいないなど、死亡した時点では
後継者が未定なのに、それを隠して周囲の人が当主の名で養子縁組を
行なうことを言います。
・・・傍系の場合は必ず前天皇の皇后か皇女を自らの皇后にして
います。
現在の一部保守派には、愛子様に旧宮家から養子を・・・という人が
いますが、そういうパターンは昔からあったのですね。
もちろん、この場合は女性天皇にはなりません。
p202
以上のことから考えると、天皇家の伝統「万世一系」は、直系の
男性がいない場合には、少し遠縁でも適任である男性を探し、
その場合は「婿入り」という形をとっているということになります。
==>> ここで光格天皇とはどういう天皇であったのかを
少しだけ確認しておきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E6%A0%BC%E5%A4%A9%E7%9A%87
「光格天皇は博学多才で、学問に熱心であり、作詩や音楽をも嗜み、
父・典仁親王と同じく歌道の達人でもあった。
また、中御門天皇系の傍系・閑院宮の出身であるためか、中世以来
絶えていた朝儀の再興、朝権の回復に熱心であり、朝廷が近代天皇制
へ移行する下地を作ったと評価されている。」
ここで思い出すのは継体天皇の件ですが・・・
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E4%BD%93%E5%A4%A9%E7%9A%87
「記紀によれば、応神天皇5世の来孫であり、『日本書紀』の記事
では越前国、『古事記』の記事では近江国を治めていた。本来は皇位
を継ぐ立場ではなかったが、四従兄弟にあたる第25代武烈天皇が
後嗣を残さずして崩御したため、大伴金村や物部麁鹿火などの推戴
を受けて即位したとしている。先帝とは4親等以上離れている。」
・・・このような経緯を古代に遡って読んでみると、
大昔から天皇家は大きな困難の時期があったのだなと思います。
今に始まった話ではないのですね。
それにしても、皇室に生まれた方々は、個人の自由もなく
大変なお仕事だと思わざるをえません。
p205
次のサイトによると、天皇家のY染色体のタイプは典型的な「縄文系」
であるD1a2a(旧D1b1)とされています。
ネットの情報が正しいとすると、東山天皇の男系子孫などを検査したとのことです。
・・・残念ながらこのサイトの信頼性を確認する方法がみつかりませんでした・・・
==> ここに書かれているサイトを参考までにリンクします。
https://www.familytreedna.com/groups/samurai-dna/about/background
「日本の天皇のY染色体ハプログループは、D1a2a1a2b1a1a(D-CTS8093)
に属することが、多くの検査によって明らかとなりました。同時に、
天皇家から分岐した系統とされる、源氏(Mimamoto clan)、平家(Taira clan)
および、東山天皇(Emperor Higashiyama)の男系子孫である
徳大寺(Tokudaiji)、住友(Sumitomo)の各家から得られたサンプルからも
同様の結果が得られました。
日本の皇統が、太古の昔から男系男子で連綿と受け継がれ、現代に至って
いることが、生物学的に確定したことは、実に驚くべきことです。」
「オクスフォード大学の遺伝学研究チームのクリス・テイラースミス
(Chris Tyler-Smith)および、カラー・レッド(Color Red)は、日本人
男性のY染色体の一塩基多型(SNPs)および縦列反復数(STRs)を解析
した結果、天皇家のハプロタイプは(D-CTS8093)に属する系統であると
結論づけました。
これは藤原氏(O-CTS10145)と並んで日本でもっとも多く子孫を残した
系統にあたります。
」
「日本民族の場合は、男系では常に縄文系を示すこのハプログループ
D(D-M64.1)系統が、優位に立ってきました。反対に女系の先祖を辿る
ミトコンドリアDNAのは弥生系統に多いD4bの系統が大半を占めます。」
・・・・男系では縄文系、女系では弥生系、というのは
どのように解釈すべきなんでしょうか・・・・
少し前の議論の中では、縄文人が様々な環境変化に適応する中で
弥生人となった、という話もありましたが。
p214
ゲノム解析では、山梨大学の安達登氏らのグループが、江戸時代の
アイヌ人のミトコンドリアDNAなどを調べた結果が公開されています。
それによると、
アイヌは、北海道縄文・続縄文人の遺伝的特徴を色濃く受け継ぐ他に、
シベリア先住民族、北方由来のオホーツク文化人、そして本州日本人の
遺伝的影響が大きい。
・・・北海道のアイヌ人は、続縄文時代以降に定着した可能性が高い。
・・・北海道の先住民族はコロボックルと呼ばれる小柄な民族(小柄な
縄文人)である。
・・・現在、北海道にある縄文遺跡は、アイヌ人のものではなく
コロボックルたちのものである。
==>> wikipediaによれば、続縄文とは弥生から古墳時代・奈良時代を含む
時代であるようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
ここには、コロボックルに関する記事はありません。
また、公的な機関のサイトには、「アイヌ文化期の遺跡」とする
ものがあります。
https://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/satsumonainu.html
コロボックルに関しては、アイヌの小人伝説としています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%9D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB
「アイヌがこの土地に住み始める前から、この土地にはコロボックル
という種族が住んでいた。彼らは背丈が低く、動きがすばやく、漁に
巧みであった。又屋根をフキの葉で葺いた竪穴にすんでいた。
彼らはアイヌに友好的で、鹿や魚などの獲物をアイヌの人々に贈った
りアイヌの人々と物品の交換をしたりしていたが、姿を見せることを
極端に嫌っており、それらのやりとりは夜に窓などからこっそり
差し入れるという形態であった。」
「現在はアイヌ人の祖先を日本人の始祖の一つとする説が流布されて
おり、コロボックル説は一般的に受け入れられていない。2008年1月
18日の産経新聞では「アイヌは縄文人の血を最も直接的に引き継いで
いるとみられている。」としている。」
「なお、2006年の第169回国会で可決された「アイヌ民族を先住
民族とすることを求める決議案」は「アイヌの人々を日本列島北部
周辺、とりわけ北海道における先住民である」とした決議で、過去
日本列島において縄文土器を使っていた人々の子孫がアイヌ人で
あるという説には言及していない。」
・・・・この本の著者は「コロボックルの遺跡」と述べているの
ですが、インターネットで探してみる限りでは、コロボックルに
ついては様々な議論があるようです。
ですので、「アイヌの遺跡」であるとするのが現状では妥当なの
かもしれません。
p217
現代日本人は縄文人の直系の子孫なのか
最大の問題は、時代の変化で環境が変わり、その環境に適した遺伝子が
増えたとしても、外部からの移民の影響と区別できないことです。
p218
残念なことに、これらの変化は、渡来人が縄文人と混血して弥生人になった
ためか、それとも単なる環境の変化のため引き起こされたのかは、単純に
遺伝子の分析をしただけではわかりません。
p220
2500~3000年前に水田稲作が日本で本格的に普及し、
結核や寄生虫が持ち込まれ、それに弱い遺伝子を持つ縄文人が
急減したので、遺伝子の多様性が急減したということでしょうか。
日本書紀には、酒で酔っ払って寝てしまった敵を討ち取る話が
出てくるので、古墳時代にはすでにこの遺伝子が相当広まって
いたらしいことがわかります。
==>> ここでは、岡田随象氏らの論文から、
「酒に弱い遺伝子」が第一位にあげられていることを
紹介しています。
この遺伝子は日本人の44%がもっているそうで、
また、これは中国長江流域由来とされているようです。
縄文時代、弥生時代の後に、古墳時代を区別して
この古墳時代と中国長江流域との関連を示唆している本も
ありました。
p230
ブリタニカ国際大百科事典によると、大和朝廷が編纂した「新撰姓氏録」
(815年)に記載されている氏は1182で、このうち326が渡来系
であり、全体の3割弱を占めるとあります。
内訳は、漢(中国大陸)が163,百済が104,高麗(高句麗)が
41,新羅が9,任那が9だそうです。
偶然かもしれませんが、これは縄文人由来とされるY染色体の割合と
ほぼ一致します。
ただ、この数字は貴族だけでしょうから、日本人全体に当てはまるか
どうかは不明です。
==>> まず漢系を検索してみます。
漢人(あやひと)
https://kotobank.jp/word/%E6%BC%A2%E4%BA%BA-427644
「① 大化前代、大陸系渡来人の一系統。漢氏(あやうじ)の部下となり、
支配下の品部(ともべ)である漢部(あやべ)を監督した者の称。
その姓(かばね)は村主(すくり)が多い。元来は五世紀初頭に
朝鮮から来た技術民がこう呼ばれたが、のち中国系と称する
渡来人を意味するようになった。→東漢氏(やまとのあやうじ)
・漢部(あやべ)。」
東漢氏(やまとのあやうじ)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%BC%A2%E6%B0%8F
「『記・紀』の応神天皇の条に渡来したと記されている漢人(中国から
一七県の人々を率いて来日、のち天皇の命で呉(くれ)におもむき、織女、
縫女を連れ帰ったという。後漢霊帝の曾孫)系の阿知使主を氏祖とする
帰化系氏族集団である。」
次に百済系はどうでしょう。
百済氏(くだらうじ)
https://kotobank.jp/word/%E7%99%BE%E6%B8%88%E6%B0%8F-1160916
「古代日本における百済出身の渡来氏族。渡来時期は一定しないが,
ほとんど7世紀後半の百済滅亡前後であろう。狭義の百済氏は公(君)
・連姓や姓のないものなどがあり,奈良時代下級官人になるものが多い。
百済王族より出る余氏や鬼室氏は奈良時代以降百済朝臣を称した。」
高句麗系には、こんな氏族名の一覧表がありました。
「日本列島に居住する帰化高句麗氏族の代表的な氏族名」
http://www.wakokugaku.org/izumo/sub104.htm
よく見る氏名としては、清原、桑原、高井、高倉、高田、田村、
鳥井、難波、松川、吉井などがあります。
・・・ちなみに、私の母方の姓もこの中にあります。
高句麗系なんですかね・・・
新羅系を探していたところ、すべてをカバーするようなサイト
を発見しました。
https://plaza.rakuten.co.jp/korealobby/diary/200603090000/
「『新羅王族系姓氏』
三宅・浮田(宇喜多)・児島・松崎・和田・沢田。
『高句麗王族系姓氏』
安達・堅部・白河・高倉・難波・高井・高麗・駒井・阿部
・芝木・賀茂・長瀬・渡部。
『百済王族系姓氏』
広野・中村・藤井・御船・大崗・錦織・菅野・眞野・三善
・飯尾・大川・大逢・太田・布施・ 町野・水浪・矢野・春野
・広井・河内・村主・砂田・高野・鬼室・室徒・桑田
・桑原・河村・ 阿久津。」
「新撰姓氏録に依ると、9世紀(千百年前)の奈良・京都地方の
官史人口の30%以上が、渡来人だつたと言う話です。
神功皇后は、新羅系。恒武天皇は、百済系。
上皇は、金大中大統領との宮中晩餐会で、遠い昔血縁だった事を、
史上初めて申されました。」
・・・私の父方の姓のルーツを検索すると、
「清和源氏頼光流の多田氏の一族小國氏。越後國刈羽郡小國より
起こる。」となっているので、これを検索して遡っていくと
結局天皇家の家系図に行き着いてしまうんですね。
まあ、多くの姓はそういうものに収斂していくんでしょうかね。
p233
歴史学者の知見は尊重すべきです。 しかし、井沢氏が言うように、
日本史は歴史学者だけに任せておくべきものでもないでしょう。
最近では、バイオサイエンスの進展がめざましく、より学際的で国際的
な視点が求められるようになってきています。
日本史を正確に読み解くためには、地学、天文学、ゲノム解析だけではなく、
英語論文の読解力が必要になるとは・・・こんなことは誰も予想して
いなかったと思います。
この著者、金澤氏は工学系のコンピュータ・サイエンス専攻の方で
あるので、歴史を様々な分野における発見から、多角的に再評価
するというアプローチをしています。
そして、その根底には、大学の恩師の言葉、
「君たちは、現在正しいとされている説と反対の説を立てなさい。
そして、それを証明しなさい。
こここそが科学の進歩なのだ!」
を肝に銘じてこの本を書いたそうです。
著者はゲノム解析の難しさを述べています。
素人的には、ゲノム解析は絶対だと思いがちなんですが、
そこにも多くの困難な技術的問題があることを正直に書いている
のは好感がもてます。
p235
本文がほぼ完成した後に、あおきてつお氏の著書「邪馬台国は隠された」
(2022年発行の改訂版)を読む機会がありました。
・・・特に面白かったのは、当時の国際情勢と崇神天皇の解説、そして
宇佐神宮の由緒でした。
==>> 実は、この金澤氏の本を読んだ時に、あおきてつお氏の著書
のこの記述があったので、順番としては逆になりましたが、
既に感想文をアップしました。
正直に言えば、あおきてつお氏のストーリーの構成力が
素晴らしかったので、私は邪馬台国九州説、
九州の他の一族が東遷をした説、邪馬台国とヤマト朝廷は
別物説、にすっかり憑りつかれています。
その意味だけでも、この本を読んだ価値はありました。
あおきてつお著「邪馬台国は隠された」を読む
https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2024/03/blog-post.html
これで感想文は終わりなんですが、
この本の表紙の色使いを見た時、その表題を見た時には、なんだか
いかがわし気な本だなと思ったものです。
しかし、最新のゲノム解析の結果などから読み解ける古代日本史の
新たな景色が見えてくるかなと思って読みました。
表題に書いてある「AIから・・・」という部分は、次回に持ち越し
と書いてあったので、少々残念ですが・・・・
=== 完 ===
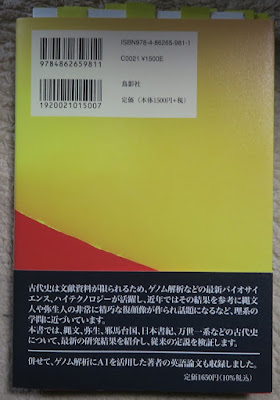

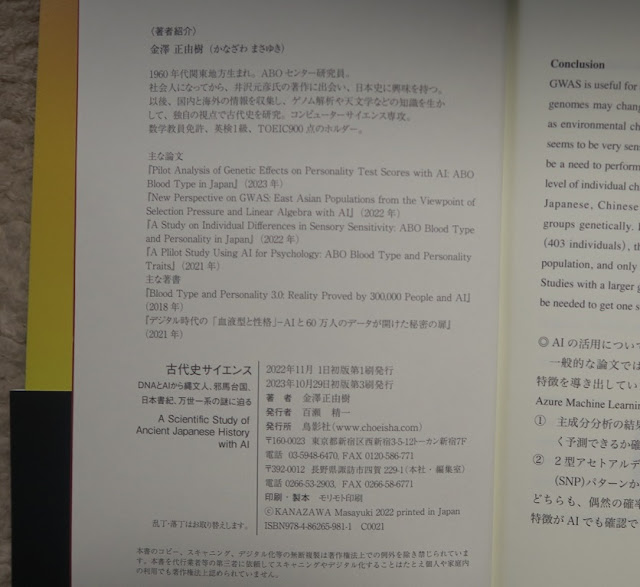



コメント
コメントを投稿