橋爪x大澤x宮台 「おどろきの中国」 を読む ―9(完)― 中国は覇権国にはなれない。 日本に中国研究所を。 ポピュリズムが外交を破壊する。
橋爪x大澤x宮台 「おどろきの中国」 を読む ―9(完)― 中国は覇権国にはなれない。 日本に中国研究所を。 ポピュリズムが外交を破壊する。
「第4部 中国のいま・日本のこれから ― 6 中国は二十一世紀の覇権国になるか」
p335
十六世紀後半あたりからオランダが覇権国である段階がある。 オランダの次に覇権国
になるのは、イギリス。 十九世紀はイギリスが覇権国だった。 そして、二十世紀に
アメリカが覇権国になって、いまはアメリカの覇権の末期的状況にある。
ある国家が覇権(ヘゲモニー)をもっているというのは、・・・・
軍事的にも、政治的にも、経済的にも、その国のパワーが圧倒的であるような状態。
p337
世界の国々がなんだかんだアメリカに文句をいいながら、アメリカの覇権を認めて
いる理由のひとつは、アメリカの行動は予測可能だからです。
透明性があり、説明責任もまあ果たしている。 過去のデータに照らしても、
アメリカの行動は容易に予測できる。
いっぽう中国の行動は、そんなに予測が簡単でない。
・・・それだけのデータや経験の蓄積が、キリスト教文明圏にはない。 日本は漢字
が読めるから少し有利だけど、情報はとれても分析脳がないから、結果は同じ。
中国自身も自分のっことを、あんまり説明していない。
・・・ある日、突然、なにか方向が変わっている、ということが起こる。
==>> アメリカの覇権は末期になっているというのは、最近よく言われていますね。
アメリカが予測が容易な国なのかどうかは、ジャパン・パッシング(日本の
頭越し)になった時期があるので、日本にとって容易なのかはやや疑問
ですが、いみじくも上で「分析脳がない」と書かれているのがその理由で
しょうか。
今までのこの本の流れから考えると、中国の場合は、多民族で膨大な人口を
抱えているから、幇の内側を除いては、以心伝心みたいなものは期待できない
と言うことなのでしょうか。
少なくとも、日本みたいに忖度はしない。
アメリカの予測可能性という点については、もしトランプ前大統領が復活
するようなことになれば、フェイクニュースをどんどんまき散らすことに
なるでしょうから、アメリカは覇権国の地位を保つことは無理になるんで
しょうね。ポピュリズムの権化みたいなリーダーですからねえ。
もしかしたら、トランプ政権がロシアと仲良くして、中国と対峙するなんて
ことがありえるのでしょうか。
p338
まとめると、いまみたいなアメリカ一極体制が、あと十年か二十年。 そのあとは、
つっかえ棒がたくさんあるアメリカ覇権体制になると思う。
中国は、覇権国家にならない。
これに乗って、アメリカを筆頭とするキリスト教文明圏側にくっついて行くというのが、
あるべき日本の基本戦略になる。
==>> ここでは、日本のあるべき姿が簡潔に述べられています。
日本が、社会主義か独裁国家にならない限りは、中国やロシアと
組むことはなさそうです。
この本は10年前に出版されていて、すでに上記の10年という年月は
経ているわけですが、さて次の10年はどうでしょうか。
図らずも、ロシアのウクライナ侵略が、この本の見方を加速している
ようにも見えます。
p340
中国は、日本よりアメリカを重視しているし、アメリカも、日本より中国を重視して
いるわけだから、日本のことは後から決まるんです。
まず、アメリカが対中関係をどうするか、中国が対米関係をどうするか。
それを日本は、適切に予測しなくちゃならない。
p341
アメリカから見たときに、せめて、日本と中国が同じぐらいに重要に見えていてほしい、
と念じている。
ほんとうは日本にとって真に恐ろしいのは、アメリカからある日、日本のことは
どっちでもいいよ、という扱いを受けることだと思います。
さらに、中国からも、「日本はわれわれにとってどちらでもよい」という扱いを受けた
ときに、日本の屈辱感はさらに深刻になるでしょう。
==>> ここでふと思い出したのが、トランプ前大統領が就任した時に、真っ先に
安倍首相がゴルフセットを持って、ご挨拶に行った話です。
今思えば、予測不可能な前大統領がどんな人物かを本人の目で確かめに
行ったのではないかと思えます。 なにせ、日本には分析脳がないそう
ですから。
おそらく、集団安保などという枠組みも、日本としてみれば、枠組みに
入っていることが安心材料になるということなのでしょう。
いまの日本の外交を見るかぎり、残念ながら、自分たちがどんなゲームの一部に
なっているのかもわかっていないし、アメリカ側につくとしても、どのような追随の
仕方がもっとも合理的なのかという評価もほとんどできていない。
外務省でずっと情報分析官をやっていた孫崎享さんは、さっきの財務省の話と同じで、
外務官僚の多くがわかっているけれども、政治家や日本人の多くがわかっていないこと
がたくさんある、とおっしゃっていました。
==>> 政治家がわかっていない・・・というのは由々しきことですね。
いわゆる市民感覚で外交を考えるというのは危険ですね。
p342
もともと尖閣諸島をめぐっては、田中・周恩来協定(日中共同声明)、あるいは
大平・鄧小平協定(「鄧小平声明」)では、「主権棚上げ」「実行支配(施政権)は日本」
「資源の共同開発」という三つが基本の柱でした。
日本の実効支配の領域に中国漁船が入ってきたら、停船要求ではなく、退去要求を出す。
それに従わなかったら、停船させて捕まえるわけだけど、そのときも「逮捕・起訴」
ではなく、「拿捕・強制送還」とする。 長年これでやってきて、自民党政権のうちは
特に問題なかった。
ところが、民主党政権になったときに、これが受け継がれなかったんです。
p343
ビデオを見る限り、海上保安庁は、退去ではなく、停船を要求した。 しかも、そのあと
前原国交大臣は、拿捕・強制送還ではなく、逮捕・送検した。 これは中国との協定に
対する二重のバイオレイションだったんです。
もちろん、外務省の人間はそのことを知っていました。
前原大臣は日中間の協定の歴史をまったく知らなかったということです。
だから、「領土である以上、主権を行使して、粛々と対処するのが当たり前である」
なんて言ってしまった。
・・・そしたら、中国の外交部報道官である凛々しい女性が出てきて、せせら笑う
ようにして、「終始一貫して、ボールは日本のコートにあり続けている」と言った。
外務省の役人はその意味がよくわかっている。 なぜかというと、日本が協定を
破ったんだから、説明責任は日本にあるんです。 中国は何も説明する必要がない。
==>> これはまた、恐ろしい話ですね。
中国からみれば、日本国内での民主党政権と外務省の間のコミュニケーション
が全くとられていないことがバレバレになってしまった。
おまけに、協定に違反をするという外交上の大失敗をやらかしてしまった。
つまりは、中国に対して、付け入るスキを与えてしまった。
それが現在まで続く尖閣諸島周辺の事態を招いてしまった?
p344
だから、全体としてはもちろんアメリカ側につくんですけど、回避できるような不利益
を中国との関係で被らないようにすることが非常に重要で、そのためには、当たり前ですが、
協定やその運用の歴史について少なくとも外務官僚なみに政治家が通暁していることが
不可欠なんです。
p345
同じようなことは原発問題でもあってね、・・・・たしかに、低線量内部被曝データに
ついては、核保有国の利害を反映したIAEAによって研究が抑止されてきた歴史が
あるので、学会の共通見解がないんです。
・・・ヨーロッパの人間はみんなそれを知っているから、市民と科学者のネットワークで
評価しましょうという自治のマインドが、この問題についてはとくに広がっているわけ
です。
だから、政府は評価しなくてよいですから、データを出してくださいと言った、やっぱり
そこで出て来たのが、「そんなことをしたら政権がもちません」だったんですよ。
p346
そんなにバカで愚かな人間は、中国にはいない。 北朝鮮にもいない。 アメリカにも
いない。 いるのは日本だけだ。 その連中をどう退治するかがまず、中国と
まともに付き合う第一歩だと思います。 この本の読者怒ってください。
小さな国ほど外交では、情勢を正しく分析し、十分リスクをわかったうえで、最善の
選択をし続けなければならないんです。
==>> ほんとうに、政権がデータすら出さないというケースと時々ニュースで
みますね。 どれほどの機密かしらないけど、真っ黒に塗りつぶされた
書類とか・・・
公文書ですら、内容が正しくないとか、捏造だとか言う始末だし。
こちらのサイトに興味深いことが書かれていました。
なぜ公文書が “後進国”ニッポンの実像
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/3223.html
「取材を進めていくと、「公文書管理は後進国」と言われても仕方のない日本
の姿が見えてきました。」
「行政文書は、はじめに起案者である職員が文書を作り、最終的に組織として
決裁されますが、多くは文書を作り始める前に周到な根回しが行われます。
このため詳しい経緯や利害関係者の発言などが書かれた資料は根回しの時点
での「個人メモ」でしか残っていないこともあるといいます。
決裁文書の改ざんなどを受け、霞が関では、経緯などを行政文書で残すこと
を危険と考え、情報公開請求の対象にならないように「個人メモ」で残すケース
が増えることを懸念する声もあります。
そうなれば、政策決定の過程を知るための重要な資料が国民の目に触れずに
消えてしまうのです。」
「各府省庁での保存期間が終了し、歴史的な公文書として国立公文書館に移管
された後は、開示するかどうかは公文書館が判断することになりますが、この
場合も所管していた府省庁の意見が考慮され、不開示情報として黒塗りされる
ことがあります。
つまり行政文書を開示するかどうかの判断に第三者が関わる余地が少なく、
文書を作成した府省庁の意向が大きく働く仕組みになっているのです。」
「アメリカでは、例えば大統領などがホワイトハウスで残したメモは、個人的な
走り書きでも、すべて公文書として保存される制度があります。」
「2014年には、「連邦記録法」が改正され、政府機関のすべての行政文書に
ついて、NARAが保存や管理の責任を負うことが明記されました。
NARAにはおよそ3000人の職員が所属しています。」
「現在、日本で公文書管理に携わる政府の担当者は、国立公文書館や内閣府の
公文書管理課の職員などを合わせても150人程度です。」
「井上さんは、「かつて日本は戦争に負けた時に公文書を次々と燃やした。
ところが東京裁判がはじまると、『なぜあの資料を燃やしてしまったんだ』、
『あれが残っていればもっと自分を弁護できたのに』と後悔した人たちがい
たという記録も残っている」
「政策決定に関わる官僚も、自分の意思決定に自信をもって、後世の歴史家や
国民の評価に耐えうるような文章を残しておくよう、積極的な意思をもって
管理にあたってほしい」と話していました。」
・・・なんというお粗末な日本なんでしょうか。
民主主義の根幹にかかわる部分が、こんなにお粗末だとは知りませんでした。
それに比べると、アメリカは腐っても鯛と言うべきでしょうか。
仕組みが素晴らしい。
p348
台湾が国民党の一党独裁政権のままでは、台湾を防衛する大義がアメリカにないから
です。 ・・・同じ中国人なのに、台湾でできた複数政党制や民主選挙が、なぜ大陸で
できないのか。 大陸に対するゆさぶり、台湾カードになる。
それは価値の問題が大きいと思います。 単に台湾を保全するのではなく、台湾の
民主主義を保全するのでなければ、正しい価値の貫徹にならないというところから、
CIAの内政干渉的な工作がなされるのですから。
これにくらべると、日本の場合、海外工作機関がないこと以上に、こうした価値
コミットメントが乏しい。
・・・単なる国防であればはるばる台湾まで出かける必要はないでしょう。
==>> ここで、台湾の民進党がどのようにできたかということが述べられて
いまして、その影に、米CIAの存在がほのめかされています。
「アメリカがサポートしてくれた」という答えが、台湾の有名な人物に
インタビューをして分かったそうです。
ここで私が感じたのは、日本人にはそこまでの外交上の価値観があるのか
ということです。
民主主義を最優先の価値観として、自律的に考えるベースが日本人にあるのか
どうかが疑わしくなってきました。
永遠にアメリカの後にくっついて行くのか・・・ってことです。
p350
中国に、軍事的な選択肢はないと国内向けに言い訳できるようにしてあげる。
そしたら、台湾を何とかしろという中国民衆の圧力を、北京政府はかわすことが
できるんです。 悪いのはアメリカだ、そして日本だ、と言えばすむ。
このことの利益がどれぐらい大きいか。
p351
沖縄をめぐって、日本とアメリカがギクシャクすることがどれだけ大きなリスクか、
よくわきまえなければならない。 基地があっても、沖縄にはいいことなんか
ほとんどないが、同時にそこに、日本はもちろん、アメリカや中国や世界の大きな
利益と人命がかかっているということも考えなければならない。
==>> いずれの国にも、対外的な事情と、国内的な事情があるわけですね。
相手の国の国内事情を理解した上での外交が必要という話。
そして、そういう外国の国内事情を分析する力があるかが外交の基礎に
なるってことですね。
しかし、この本では、日本にはそのような分析脳がない、と言っている。
p352
アメリカは矛盾しているんですよ。 台湾は中国の国内問題であって、中国は一つで
あると同意している。 でも同時に、民主的に選ばれた政権のもとにある台湾を、武力
によって「解放」することはアメリカは認めない。実力で防衛すると、台湾に
対する防衛義務も主張しているんです。 ・・・考え方が、分裂しているんです。
アメリカの専門家は、台湾問題に関して、平和的な統合ならアメリカは容認するしか
ないと、議論した結果、ほぼ結論を出しているんです。
p353
日本はこの問題を、じつは考えてすらいない。 アメリカは考えていますよ。
「日本は考えていますか?」「うーん、考えていないみたいですね」。
つまり、ヴォーゲル先生は日本の官僚や政治家と大勢会うでしょうが、台湾問題の
基本がどういうものか、わかっているひとと話したことがないという意味です。
北朝鮮についてもほぼ同じだと思います。
==>> ここは非常に重要なことに見えます。
アメリカは変わり得るということですね。そして、それはほぼ決まっている。
日本は、上記の尖閣諸島に関する日中間の取り決めについても政治家自身が
ことの重要性を分かっていなかった。
この台湾問題に関しても、どうやら米中の歴史的ないきさつと今後の
想定に関しては考えていないらしい。
つまり、歴史、文書を燃やしてしまって、頭の中にあるものを燃やして
しまって、すべてを「想定外」という言葉に置き換えてしまうという体質
になっているらしい。
これでは進歩は望めませんね。
国会議員はなんのために大勢いるのか・・・と思います。
国会議員を半分にして、あとの半分に行政・外交文書管理をやらせた方が良さ
そう。
p357
内政に関することでさえも、肝心なことはアメリカの意思を読みながら行動している
と思われる。 ・・・日本がかくもたくさんの原発をもった理由、いまだに決然と
脱原発を選択できない理由も、アメリカに関係している。 ようするに、アメリカは、
日本が原発を造り続けることを望んでいて、そう望まれている以上は、日本としては
これを拒否できないのです。
==>> そうでしたか。 こういうところでも、アメリカを「忖度」している
わけですね。 アメリカは、日本が核戦力を自前で持つことを期待して
いるのでしょうか。その辺りのアメリカの本音が知りたいですね。
原発に関していえば、私はミサイルの標的になる可能性が高いし、地震や
火山などの自然災害の脅威も差し迫っているので、将来型の分散型の発電に
していくべきじゃないかと思います。
技術的なことはさっぱり分かりませんが、新技術を開発して、そのことで
新しい産業を起こしていってもらいたいと思うんです。
p359
日本と韓国と中国は、長い目で見たら朝鮮半島は統一しなくちゃいけない、そういう
日が来るはずだとは思っている。 けれども、北朝鮮が民主化したときに生じるリスク
を引き受ける覚悟が、いまのところないと思うんですよ。
日中韓がひそかに思っているのは、「北朝鮮がもう少しましになってから、韓国と
統合してくれればいいな」みたいなことです。
でも、北朝鮮の民主化をただ待っていても、永遠に民主化はしないでしょう。
核問題を含む北朝鮮の問題を、最終的に解決するためには、北朝鮮に民主化して
もらうしかない、ということです。
==>> ここでは、東西ドイツが統合された時に、西ドイツを中心とした周辺諸国が
「倒壊によるリスクを覚悟をもって引き受けた」ことが述べられています。
そのような覚悟がなければ、いつまで経っても朝鮮半島は安全にはならない
ということなんです。
p360
外務官僚もそれがわかっていて、拉致問題の解決と核問題の解決の一石二鳥を狙う
ロードマップを描いたんです。
p361
まず、北朝鮮との約束通り、拉致被害者を一度きちんと北朝鮮に返す。
そのリターンとして、北朝鮮がさらなる拉致被害者の存在を認める。
そうしたら、日本が経済援助やアメリカへの口利きに向けて動く。
北朝鮮はお返しに、核開発凍結に向けたか前を示す・・・・・。
アメリカにとっては拉致問題より核問題のほうが優先順位が高いですから、核問題解決
に向けたロードマップの中に拉致問題を組み込む以外にありえない。
ところが、まずブッシュ・ジュニアがポピュリズムの観点から突如、北朝鮮封じ込め
政策のほうに舵を切り、同時に日本でも安倍晋三官房副長官が「政権がもたない」と
いうふうにポピュリズム的な方向からバイアスを思い切りかけることで、こうした
ロードマップをつぶしちゃったんですよね。
・・・いきなり北朝鮮から見ると予測不可能な行動に転じたわけです。
==>> なんと、なんと。 拉致問題が座礁してしまったのは、日米側の
ポピュリズムという国内問題にあったんですか。
まあ、これじゃあ、外務官僚もやってらんないですね。
p364
日本の場合、政策的意思決定を支えるこうした専門家の層が薄くてあまりに貧弱です。
そんな状態で、アメリカや中国との連携なしに、独自に動くのはとても危険です。
p365
軍事行動のオプションがないとするなら、北朝鮮の体制維持のカギを握るのは中国で
あり、アメリカがそれに次ぐ。 日本は交渉しようにも、その舞台にあがることさえ
できません。
「アメリカと中国は本当の友人になれますか?」とヴォーゲル先生に聞いてみた。
答えは、「政治家同士、学者同士、ビジネスマン同士の個人的関係は、築けている。
人間として互いに信頼しているけれども、価値観がちがうから、国として友人同士
であると言えるのにはすごく時間がかかると思う」でした。
両国の国益やものの考え方や目標には、埋められない大きなギャップがある、という
ことなんです。
p366
個々人としての中国人と、個々人としての日本人を比べてみると、たいていの場合、
一対一だったら力負けすると思う。とくにリーダー同士の場合。
儒教の行動原理。儒教は、個人プレーの集まりなんです。 それに対して、日本人の
場合はそういう習慣がない。 大事なことは集団で決め、組織として行動するから、
自分の考えや行動を相手に説明もできないし、自分でも納得できない。
これでは、負けてしまう。
==>> 中国人には意識的ではないにしても、儒教が染みついている。
日本人にはそのような行動原理がない。あえて言えば、もしかしたら
ぼんやりとした曖昧な神道的なものかもしれない。
神道的なもので組織的に戦争を闘った。 でも、個人的な責任範囲が
曖昧で、無責任な集団でしかなかった。
p368
一般人のレベルで言っても、アメリカ人が中国の歴史について知っている量と、
日本人の高校生ぐらいが知っていることを比べれば、日本人のほうが上でしょう。
日本はそういう意味で有利な立場にあるわけですから、中国との関係において、
アメリカがまず仲良くしなければいけないのは日本なんだという構造をつくることが、
いま重要だと思いますね。
p369
加藤紘一さんは、外務省のチャイナスクールであったわけだけど、「そうした議論
ができるような雰囲気が、外務省からも政権からも失われた」とおっしゃって
いました。 当時は自民党政権でしたけれどもね。
p370
歴史についてギャアギャア言われるので、日本人は、言い訳をしようと考える。
そうじゃなくて、これをメッセージとして受け取らないとダメなんです。
中国がなんで歴史問題をいろいろ言うか。それは「歴史問題さえ片付けば、一緒に
やりたいことがたくさんありますよ」と言っているんです。
それなのに日本が言い訳するから、相手は当惑する。
・・・全然ピンと来ていないひとたちだ、と中国では思っている。
==>> この辺りを読んでいて頭に浮かんだのは、日本学術会議の問題と
大学の問題です。 政治家が自分に都合の悪い学者に対して、無用な
介入をしたり、科学技術に偏った助成をするというようなことです。
科学技術が発展することは素晴らしいことなんですが、最近は、
ユヴァル・ノア・ハラリ著「ホモ・デウス」や カズオ・イシグロ著の
いくつかの小説でも語られているように、人類の危機をももたらし
かねない将来につき進んでいるようです。
そこには、哲学や倫理の分野での新しい境地が必要でしょう。
外交が国の運命を大きく左右するということを、ここまで学んできた
わけですが、それであれば、やはり海外の国々のことをしっかり分析
できるだけの頭脳を育てなくては、日本の将来が危うくなるという
ことではないかと思います。
もっとも、最近の大学教育は、大学院も含めて言うと、欧米や中国の大学に
比べて、研究者が不安定な地位で貧しい環境にあるということですので、
海外にヘッドハンティングされる有様ですから、将来が思いやられます。
p370
中国はまだローカルな文明で、世界化されていないから、外国に対してもつい同じ
ようにふるまってしまう。 たまたまアメリカとは波長が合うから、ある程度わかり
合えるんだけど、日本人はわからない。
p371
中国が困っていることを日本がよく分析し、理解して、中国に代わって世界に向けて
言ってあげる、なんていうのもいい。
p373
台湾に関して言えばね、アメリカがそういう政策をとっているんだったら、
日本もそういう政策をとるかどうか早く考えて、で、台湾が平和的に大陸と
一体化すると宣言したとたんに、もうアメリカはそれを認めると決めているわけ
だから、一体化に決まり。
ゆえに、その瞬間に、アメリカよりも早く、「認めます」と日本政府が言う。
一時間でも早く、三十分でも、十秒でも早く、ね。
p374
アメリカよりも早く言うために宣言文まで用意して、抽き出しに入れておかないと
いけない。
日本はアメリカがどう反応するかを見てから言おうといつも思っているから、
ダメなんですよね。
==>> さて、首相あるいは外務大臣の抽き出しの中には、宣言文が入っている
のでしょうか・・・・・
p375
アメリカの法学者キャス・サンスティーンによれば、昨今は民主主義が集団的な
極端化を招きがちで、その背景にあるのは、第一にグローバル化がもたらす格差や
貧困などによる不安や鬱屈、第二に不完全情報です。
この二つの条件がそろうと、不完全な情報しかない領域で極端な発言をすることで、
自分や周囲の溜飲が下がり、集団内での承認も得られることになります。
・・・不完全情報の状態を完全情報化にむけてシフトさせて、<溜飲厨>や<承認厨>
の影響力を排除しよう。
p376
日本からのいいサインは、中国研究所をつくることです。 見栄えがいいプランで、
「中国をこれから重視するから、研究所をつくります」といって、予算を出す。
ついでにアメリカ研究所もつくる。 これだけで大きなサインになるんです。
そうですね。 アカデミックなものとポリティカルなものが直結しているところが
中国の特徴ですよね。
==>> なるほど、この辺りは、昨今の世界の状況を当てているというか、
この本が書かれた10年前からそうだったのか・・・・
端的には、トランプ前大統領が大統領選挙の運動をやっていた2016年ごろ
から始まったと考えていいんでしょうかね。
非科学的な言説や陰謀論などが飛び交って、アメリカを分断してしまった
わけですが・・・
p379
「あとがき」
本書では、中国のことを考えるとき陥りやすい勘違いや落とし穴など、目をつけるべき
ポイントに集中した。 こういう筋道で考えていくと、しっかり考えられる。
中国の人びとと手を携えられる。 そういう考え方の基本スタンスが、提案してある。
==>> やっと読み終わりました。
最初に書いたように、この本は、すべてのページに、私にとっては
驚きの宝のような事柄が書かれていたので、目を開かれる思いでした。
ぜひ、皆さんも、すべてのページに目を通していただきたいと思える
私の推薦本です。
日本の外交が、ポピュリズムに陥ることなく、50年、100年先の、対米、対中関係を
俯瞰しながら、「想定外」と言うこともなく、将来を切り開いて行って欲しいと、
老い先短い高齢者は願うのであります。
===== 完 =====
==============================
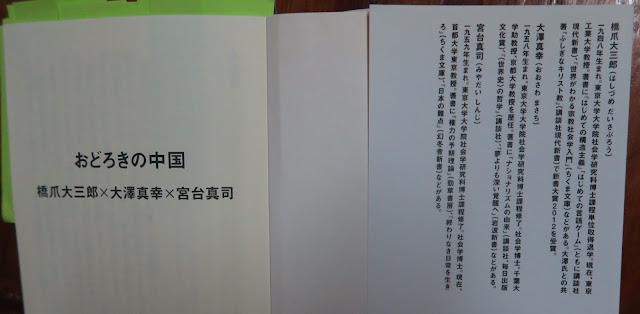



コメント
コメントを投稿