田中健夫著「倭寇 海の歴史」を読む ― 1 ― 松浦党などの倭寇を朝廷はコントロールできなかった。 遣元使船(寺社造営料唐船)が禅をもたらした
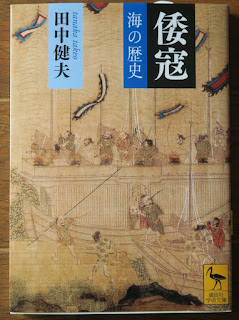
田中健夫著「倭寇 海の歴史」を読む ― 1 ― 松浦党などの倭寇を朝廷はコントロールできなかった。 遣元使船(寺社造営料唐船)が禅をもたらした ここしばらくは、神道、神社、そしてその起源ということで、何冊かの本を読んで きたのですが、そこで思ったのが、国境というものがまだ判然としなかった時代に、 どのような地域の文化圏があったのか ということです。 そして、真っ先に頭に浮かんだのが 倭寇の存在 です。 フィリピンに過去15年ほど住んで、その間に、フィリピンの歴史教科書も少し 読んだのですが、そこにも倭寇の痕跡が書いてありました。 と言うことで、今回は倭寇を読んでみます。 まずは、 日本の国境というものがいつ頃意識され固まったのか を検索したところ、 下のような説明がありました。参考まで。 https://q.hatena.ne.jp/1224305977 「日本では、江戸時代後期にすでに欧州で出来つつあった国家のあり方を持つ ロシアの 接近という外的要因と国学の大成による内的要因 、さらに江戸幕府崩壊後の明治維新の 中で、現在の我々が使用する日本語の作成や帰属意識を作る国家の歴史を作り、教育して いった。また、そこでは中国との差異化による固有性の発見と欧州への同一化によるアジア における優越も思想的な問題として行われていたという。これによって、 日本が漢語による アジア圏から脱却し、一国家として他とは国境を持って一線を画すようになった のでは ないかという。 ちなみにこれは、某大学で行われた講義で扱われていた部分をかいつまんで書いたもの なので、その講義を行った教授の思想・考え・偏見が入っていることを忘れてはならない ことも付け加えておきます。」 また、別の角度で、 日本地図というものがどのように作られてきたのか をチェックして おきましょう。 国境という意識はないようですが、こちらの室町時代の地図が日本列...
